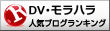DV・モラハラ加害者の価値観はどこから?育った家庭と性別の価値観が作る暴力の連鎖

DV・モラハラの加害者の価値観は、単なる性格の問題ではありません。
幼少期の家庭環境や生い立ち、さらに「男性は強くあるべき」「女性は支える存在であるべき」といったジェンダー(性別役割)意識が大きく影響しています。
父親が母親に暴力やモラハラを行う家庭で育った場合や、支配と服従の構造が当たり前とされる環境では、「自分の考えが正しい」「相手を従わせるのが当然」という価値観が形づくられやすくなります。
本コラムでは、DV・モラハラ加害者の価値観がどのように生まれるのか、育った家庭や社会的背景がどのように暴力の連鎖に関わっているのかを整理し、家庭の中で暴力を生まないための視点を考えていきます。
目次
幼少期の家庭環境とDVの関連性

DV・モラハラ加害者の多くは、暴力や支配のある家庭で育っています。
父親が母親を支配する姿を「家庭の普通」として見てきた子どもは、その構造を学び取り、自分の家庭で再現してしまうことがあります。
心理学者ジェームズ・ダットンの「虐待的パーソナリティ論」によると、以下の3つの要素が組み合わさると、成人後に虐待的な傾向が形成されやすくなるといわれます。
- 幼少期に虐待や暴言を受けた経験
体罰や暴言、感情的・身体的な虐待が、心理的な基盤を揺るがします。 - 恥辱や批判による自己価値感の低下
「お前はダメだ」といった恥辱的扱いや、期待に応えられなかったことへの叱責が自己価値感を低下させます。 - 親の感情が予測できず、安心して依存できない環境
親の気分や態度が不安定で、安心して依存できない環境は、愛着形成を不安定にします。
このような環境で育つと、「自分は愛されない」「支配される前に支配しなければ」というゆがんだ防衛反応が大人になっても残ることがあります。
加害者の価値観と行動の特徴
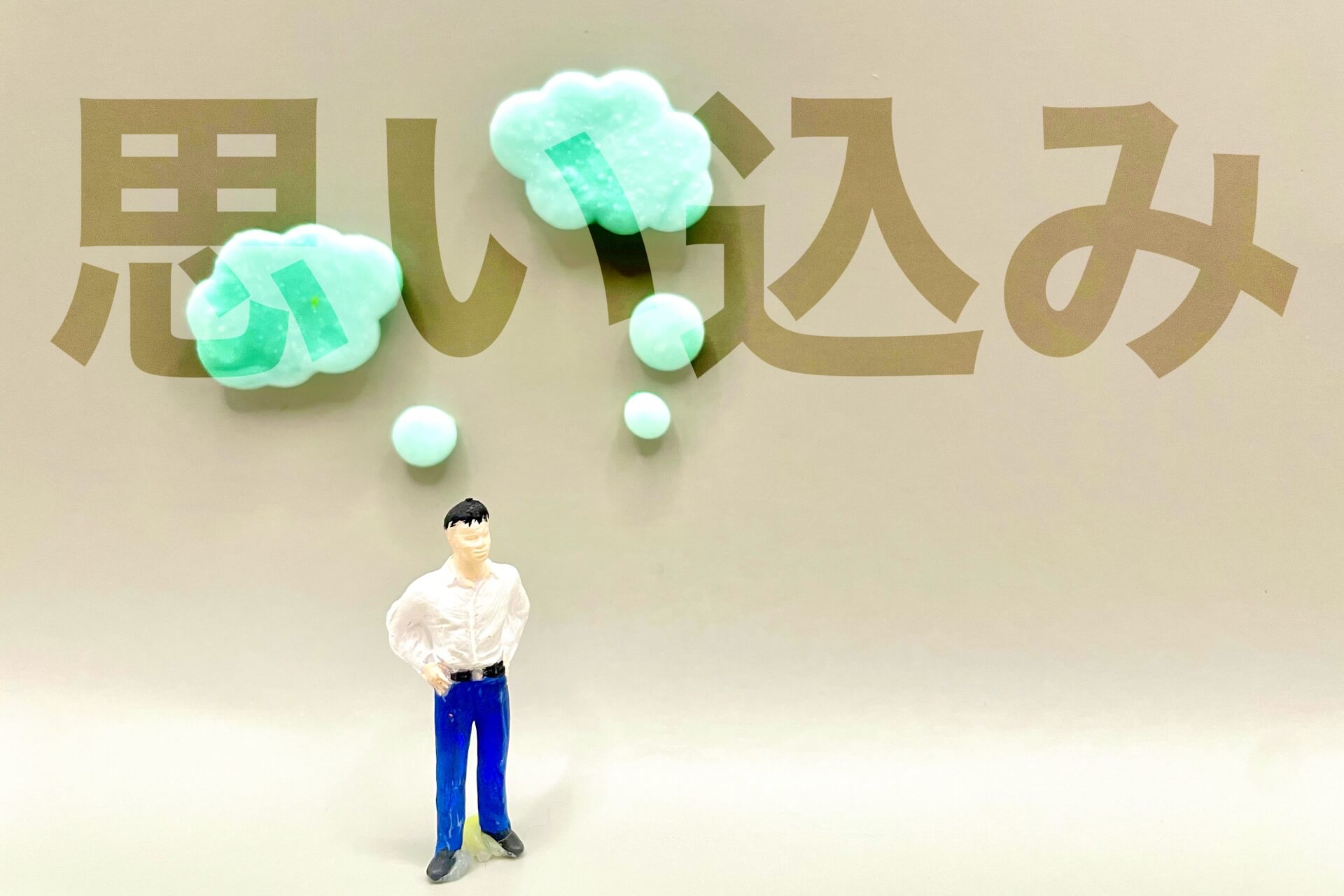
DV・モラハラ加害者に共通するのは、「自分の考えを絶対視する傾向」と「相手への共感の欠如」です。
彼らの行動や考え方には、次のような特徴があります。
- 「夫は外、妻は家」「妻は夫を尊重すべき」と信じている
- 子どもへの暴力を「しつけ」や「愛のムチ」と正当化する
- 反論されると「自分が否定された」と感じ、怒りで支配する
- 自分は“被害者”だと思い込み、責任を回避する
- 家族に依存し、支配することで安心を得ようとする
こうした価値観の背景には、家庭内の支配構造に加え、社会全体に根付くジェンダーの呪縛があります。
加害者の価値観はどこで形成されるのか

1. 家庭の中の“支配と服従”のルール
幼少期から「夫は外・妻は家」「妻は自分を立てるべき」という価値観を見て育つことで、「男は支配する側」「女は従う側」という無意識の前提が作られます。
父親が母親に暴力を振るう家庭では、子どもはそれを「家庭の普通」として覚えていきます。
暴力だけでなく、沈黙や無視も“権力の使い方”として学んでしまいます。
2. 「暴力はしつけ」「愛のムチ」という歪んだ正当化
子どもを叩くことを「しつけ」や「愛情表現」として許されると信じます。
怒鳴る・物に当たる・不機嫌で支配することをDVとして認識していません。
その行動を「正そうとしているだけ」「悪いのは相手」と正当化します。
3. 「自分の価値観が唯一正しい」という思い込み
加害者は「自分の考え=常識」と信じ、反論されると支配的に振る舞います。
背景には、閉鎖的な家庭環境で育ち、他の考えを理解・尊重する経験がほとんどないことがあります。
4. “自分は被害者だ”という心理構造
DVで家族が苦しんでも、「自分が大事にされていない」と感じます。
責任を回避するために、被害者意識にすり替える心理が働きます。
5. 根底にある“満たされなさ”と依存
加害者は「家族への依存」「愛されなかった子ども時代」「自分への嫌悪」を抱えています。
その痛みを隠すために支配という形で安心を得ようとします。
6. 社会的背景とジェンダーの呪縛
「男性は強く」「女性は控えめに」という価値観は、いまだ根強く残っています。
これらは家庭内の力関係を固定化し、「男性が中心であること」が当然という空気をつくります。
その結果、「怒鳴る」「命令する」「コントロールする」といった行為を、“責任感の表れ”や“愛情”と誤って認識するケースも少なくありません。
暴力を生む価値観から離れるために、家庭内でできること

研究によると、虐待を受けて育った人の約半数は、自分の子どもを虐待しないといわれています。
「連鎖は必ず起こるわけではない」という事実は希望でもあります。
連鎖を断ち切る鍵は、
- 自分が受けた育てられ方を客観的に見直すこと
- 社会的サポートを受けられること
- 家族以外の誰かと健全な関わりを持てること
つまり、暴力や支配のある家庭では、当事者だけで解決するのは難しいのです。
外部のサポートを受けることが、加害者にも被害者にも不可欠です。
家庭の風通しを良くする
家庭では、意見や感情を自由に話せる雰囲気をつくることが大切です。
「言っても無駄」「怒られるかも」と感じさせない関係は、支配ではなく信頼を育てます。
子どもが安心して話せる家庭は、暴力を“普通”だと思わずに済む土壌になります。
ただし、父親の暴力があった直後は、母親が「怖かったこと」を無かったことにしてしまいがちです。
子どもにとって、恐怖体験を話せない状況は、暴力そのものより心理的に危険です。
自分と子どもの感情が落ち着いた1~2日後に、次のことを意識してみましょう。
- 父親(母親)のどの行動が許されないかを、悪口を言わず、かばうことなく正確に説明する
- 自分や子どもに落ち度がないことを伝える
- 子どもが怖かった気持ちや混乱した感情を言える場をつくる
- 「怖かったね」と共感しながら受け止める
こうすることで、子どもは暴力を無かったことにせず、正しく理解でき、自分の感情を整理する経験ができます。
母親も、子どもと一緒に感情を整理することで、家庭内の信頼関係を少しずつ取り戻せます。
家庭の問題をオープンにする
家庭の問題を「恥ずかしいこと」「外に言ってはいけないこと」と閉じ込めてしまうと、苦しみは見えないところで深くなっていきます。
誰にも気づかれないまま、心の中で孤立が進み、自己否定や無力感が強まっていくのです。
たとえ加害の状況がすぐに変わらなくても、信頼できる人や専門機関に被害の状況を話し、自分の怒り・悲しみ・つらさをそのまま伝えること。それだけでも、被害者が心の健康を取り戻す力になります。
安全な環境を最優先にする
もし家庭内で暴力や強い支配があるなら、まずは安全を確保することが最優先です。
別居や避難は簡単ではありませんが、命と心の安全が守られなければ、修復や対話は成立しません。
離婚や同居の形に関係なく、安心して気持ちを話せる環境を持つことが、回復の基盤になります。
まとめ:加害の背景と、責任は別のもの

DVやモラハラの加害者が育った環境には、多くの場合、暴力や支配の構造があります。
それは事実として理解すべきことであり、「人は環境に影響される」ことを示しています。
しかし、どんな過去があっても、いま誰かを傷つけていい理由にはなりません。
「つらい過去がある」「愛し方を知らなかった」という背景と、いま目の前で起きている加害行為は、まったく別のものです。
あなたがされた暴力や支配には、どんな“事情”があっても、正当化できる理由は一つもありません。
加害者の過去を理解することと、あなたが我慢することは、まったく違います。
過去の連鎖を断ち切るためには、まず「これは暴力だ」と明確に認識し、
“加害者の背景”と“あなたの被害”を切り離して考えることが大切です。
参考文献
DVモラハラ加害者たちの体験談~加害更生プログラムで自分と向き合う~DV加害更生プログラム「たんとすまいる」参加当事者の会(著),2022年
中村 正「親密な関係性における虐待・暴力と加害者臨床論──虐待的パーソナリティ論の検討をとおして──」『立命館産業社会論集』第46巻第1号、2010年6月
加害者の価値観や背景についてはこちらの記事も参考になると思います
↓↓↓↓
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


DVモラハラから抜け出せない共依存夫婦とは?特徴と心理、抜け出す方法について解説 | DV・モラハラ・離婚…
「DVやモラハラを受けていても、なかなか相手から離れることができない」そのような関係は「共依存」という「関係性の依存症」によるものかもしれません。このコラムでは、…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

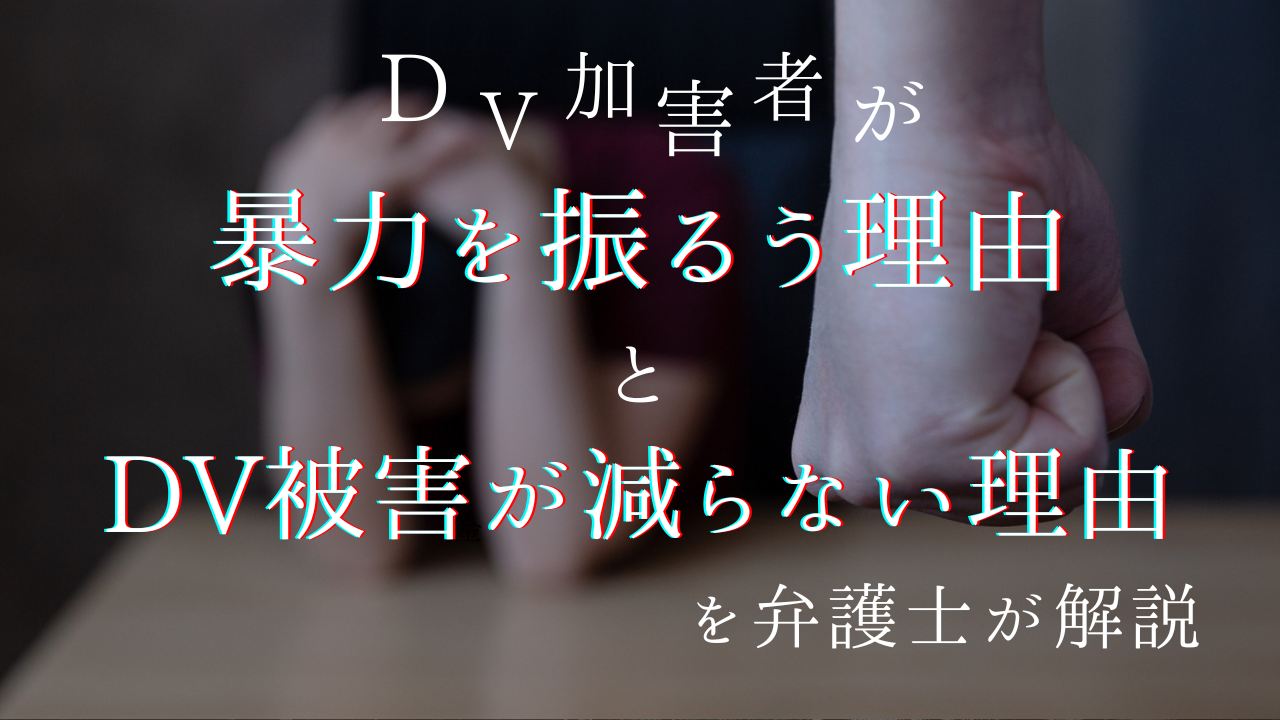
【DV】DV加害者が暴力を振るう理由とDV被害が減らない理由を弁護士が解説 | DV・モラハラ・離婚で弁護士を…
2001年のDV防止法の成立・施行がきっかけでDVという言葉が周知されるようになり,現在では”DV”という言葉の意味を知らない人はほとんどいないのではないかというような状況…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

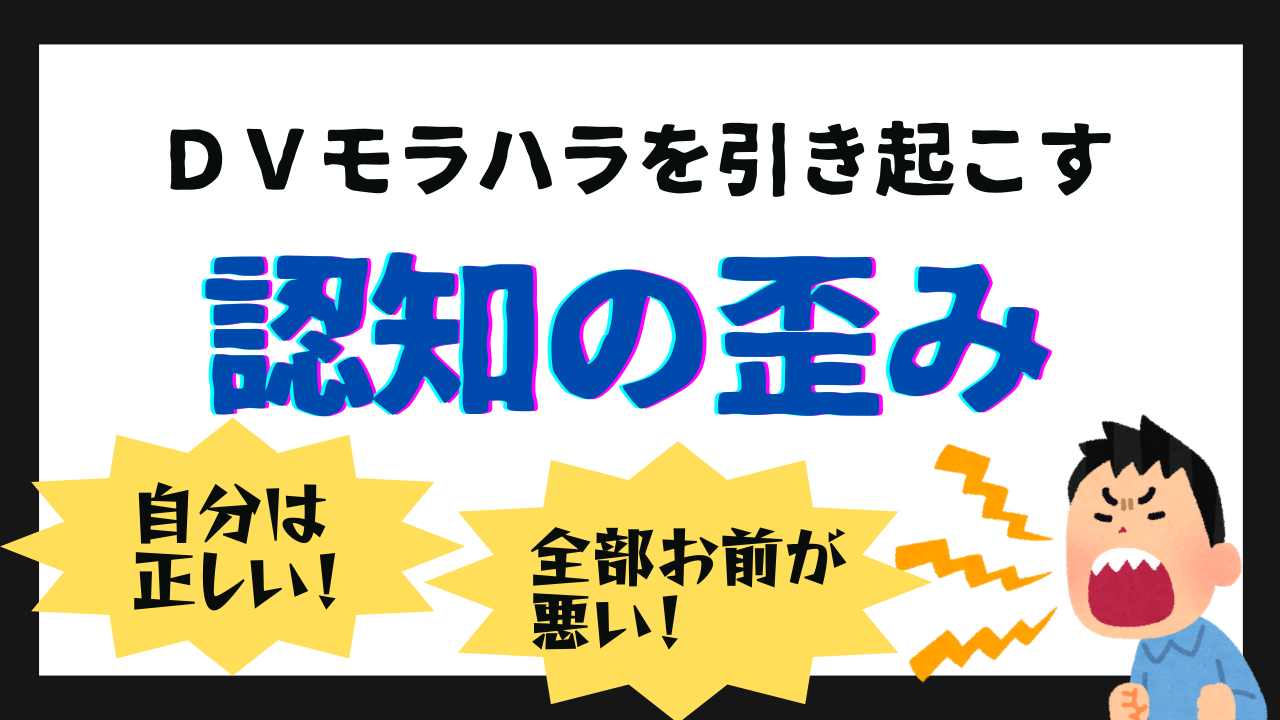
DV・モラハラ加害者・被害者に共通する思考パターンとは?「自分が正しい」と思い込む心理学的理由を解説 |…
DVやモラハラの加害者は「自分が正しい」と思い込み、被害者は「自分が全部悪い」と感じる傾向があります。このコラムでは、心理学的視点から加害者・被害者に共通する認知…