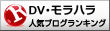DV・モラハラ夫が親権や面会交流権を欲しがる理由と母子を守る安全対策
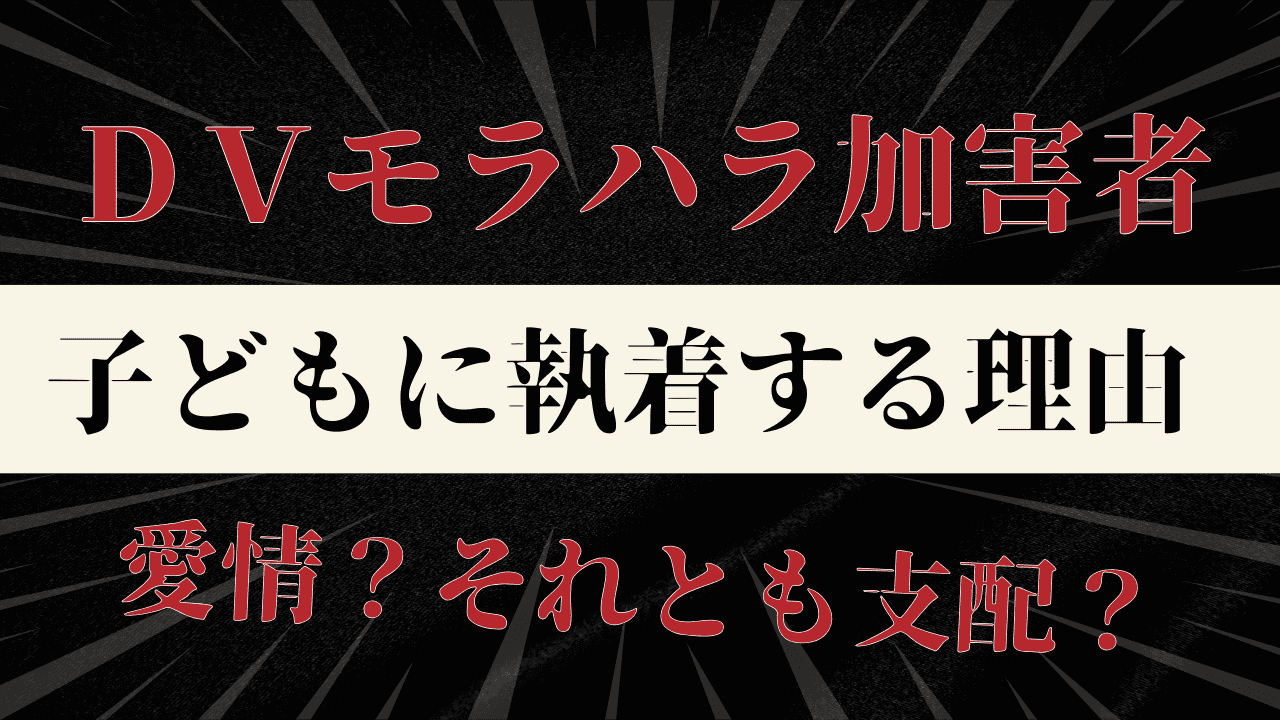
離婚や別居後、これまで子育てを相手に丸投げしていたDV・モラハラ加害者が、突然「親権を取りたい」「面会交流をしたい」と強く主張してくるケースは少なくありません。
被害者にとっては不可解で不安をあおる行動ですが、実は加害者には共通する心理パターンが存在します。
共同親権導入も近い今、親権や面会交流をめぐるトラブルはますます複雑化しています。
このコラムでは、加害者が親権・面会交流に執着する理由、裁判で生じやすい誤解、そして被害者と子どもの安全を守るための具体策を解説します。
目次
加害者が親権・面会交流に執着する理由

米国の研究では、虐待を行う父親は非虐待の父親に比べ、2倍以上の頻度で単独親権を求めることが報告されています(Smith & Coukos, 1997)。
DV・モラハラ加害者が、別居後に突然「親権」や「面会交流」に強くこだわる背景には、特有の心理構造があります。
1.被害者を見下す認知
自らの暴力を正当化し、「母親が未熟だから逃げた」「自分の方が子育てにふさわしい」と思い込む。
2.支配欲
別居で失った支配力を取り戻すために、親権・監護権を主張し続ける。
3.報復目的
親権や面会を盾に、母親を経済的・精神的に追い詰める。
4.汚名を晴らすため
「子どもを連れて出て行かれた親」と周囲に見られることに耐えられず、親権を獲得して「立派な父親/母親」という社会的評価を得たい。
5.歪んだ自己認識
自分の暴力や子どもへの影響の重大性を過小評価し、「自分は良い親だ」と信じて疑わない。
6.母親への影響の過小評価
母親が抑うつや心身の不調に苦しんでいても、「母親に問題がある」と考え、自分の暴力の影響を認めない。
7.経済的・法的譲歩を引き出す
慰謝料や財産分与で優位に立つため、親権・面会交流をちらつかせる。
8.暴力が子どもに及ぼす影響を無視
家庭内の緊張や暴力が子どもに深刻な悪影響を与えることを理解していない。
(参考:Bancroft & Silverman『DVにさらされる子どもたち』)
裁判所でDV・モラハラが誤解されるケース

研究によれば、母親がDVを受けている家庭では、子どもも虐待を受ける頻度が高いことが示されています(Jouriles et al., 2008)。
しかし裁判所では、「母親への暴力」と「子どもへの影響」が切り離されて評価されることも少なくありません。
その結果、母親が子どもを守るための行動が「不適切」と誤解されるケースがあります。
実際、オーストラリアではかつてフレンドリーペアレントルールが制定されており、DV被害者が加害者との交流を制限すると「非友好的」と判断され、虐待の主張が制限されるなどの不利益が生じる問題がありました。
そのため、このルールは廃止され、現在ではDV被害者が安全を確保する行為が親権判断に不利にならないよう配慮されています。
このような背景から、DV・モラハラ加害者との親権争いは、一人で対応するのは非常に難しく、DVやモラハラに詳しい専門家の支援を受けながら行動することが重要です。
加害者が裁判所で使う典型的な手口
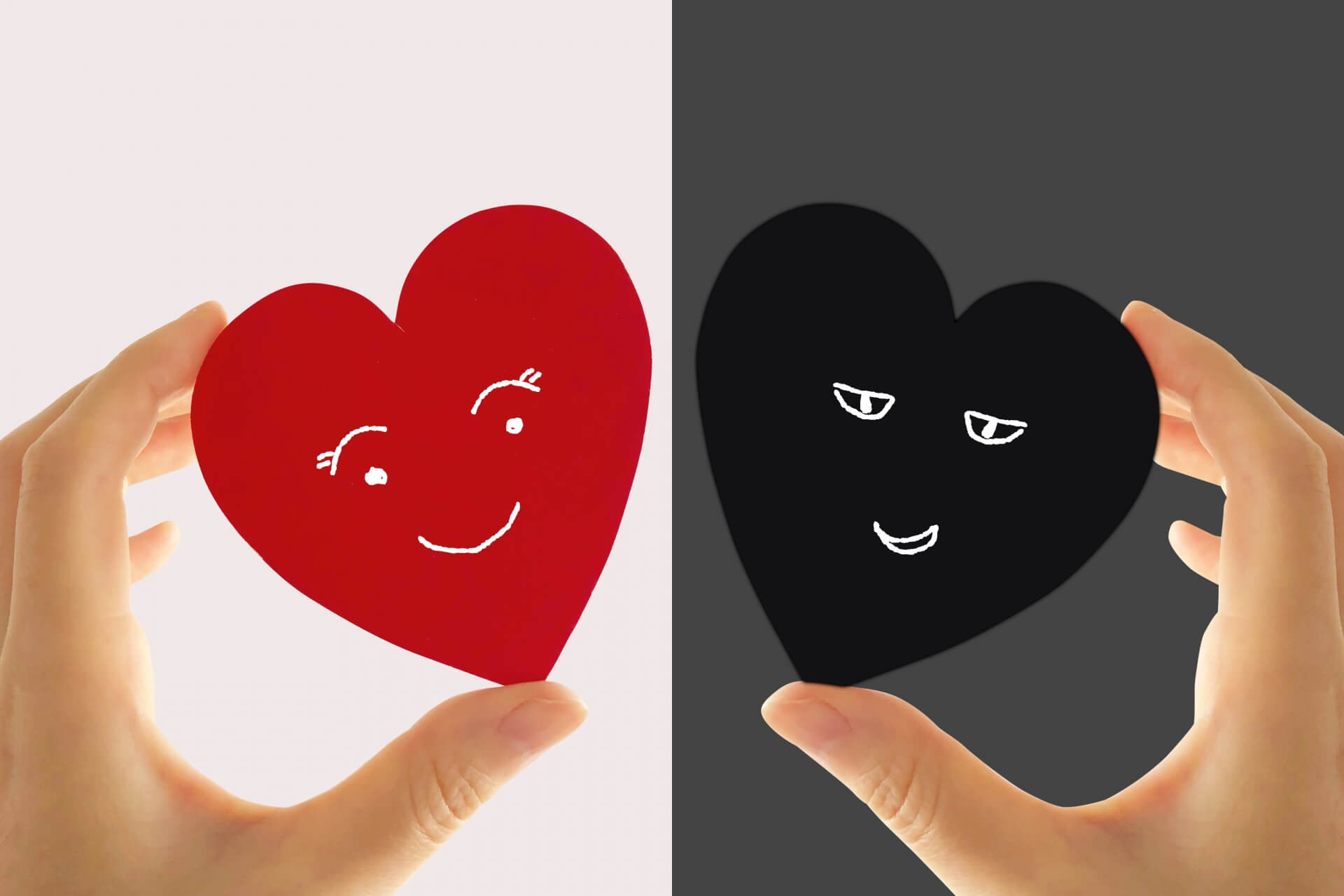
- 「虐待する人ではない」と印象操作
- 裁判官の前で穏やかに話し、子どもへの愛情を大げさに強調する。
- コミュニケーション重視の姿勢を演出
- 「友好的に共同養育したい」と主張。
母親が子どもを守るために接触を制限することを主張する場合、母親が友好的ではないと判断される可能性がある。
- 「友好的に共同養育したい」と主張。
- DV被害を虚偽だと疑わせる
- 「片親疎外」「でっちあげ」と主張し、母親のDV被害を虚偽に見せかける。
- 調停や裁判を通して虐待する
- 精神的苦痛を与えることを目的に面会交流の増加、養育費の引き下げなどの要求をしたり、陳述書でも相手を貶めるような記載をする。
別居後の母子の安全確保

母子の安全・子どもの情緒的回復を第一にする
加害者はしばしば「父子の絆を断とうとしている」「子どもにとって父親との接触を断つことは子どもの福祉に反する」と主張します。
また、共同親権の導入により、「子どもが嫌がっても面会を優先すべき」「子どもの回復のために父親と交流させなければ」と考え、被害者が自分の受けた傷や恐怖を無視して加害者との交流を続けてしまうリスクもあります。
しかし、加害者との絆を深めることは確かに重要ですが、子どもにとって最優先すべきは安全で安心できる家庭環境を整えること、被害者と子どもの絆を回復すること、そして子どもが「母親も回復している」と実感できることです。
裁判所では、面会が子どもにとって危険と判断される場合、面会交流が制限されることもあります(例:手紙のやり取りや写真送付のみ)。
面会交流は第三者機関を利用する
面会交流は、加害者が母親を支配したり、子どもを危険にさらす手段として利用される可能性があり、その場合、子どもの情緒的回復が阻害されます。
また、子どもが加害者の自己中心的な振る舞いや攻撃的な態度に嫌気を感じ、面会を拒否するようになるケースもあります。
そのため、第三者機関を介して面会を行い、母子が安心して交流できる環境を整えることが、子どもが健全に父子の絆を育む上で大切です。
監督なしでの面会は、父親が自らの暴力の責任を認めているか、子どもが時には父親の行動や権威を疑い、嫌なことは拒否できるか、子ども自身が望んでいるかなど、子どもにとって安全と判断できる条件が揃うまでは慎重に行う必要があります。
まとめ

加害者が親権や面会にこだわる理由は、必ずしも「子どもへの愛情」ではありません。
支配欲・報復・自己正当化が背景にあるため、母子の安全と安心を最優先に対応することが大切です。
「子どもを守る」「自分も守る」—この視点を忘れず、DV・モラハラに詳しい専門家の支援を受けながら行動しましょう。
参考文献
- ランディ・バンクロフト/ ジェイ・G・シルバーマン(2022)『DVにさらされる子どもたち』
- Smith, R. & Coukos, P. (1997) Fairness and Accuracy in Evaluations of Domestic Violence and Child Abuse in Custody Determinations
- NCJFCJ (2022) Parenting Plans After Family Court Findings of Domestic Violence
- Jouriles, E. N., et al. (2008) Child Abuse in the Context of Domestic Violence
離婚と子どもの問題についてもっと深く知りたい人は、こちらの記事も参考になると思います。
↓↓↓↓
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

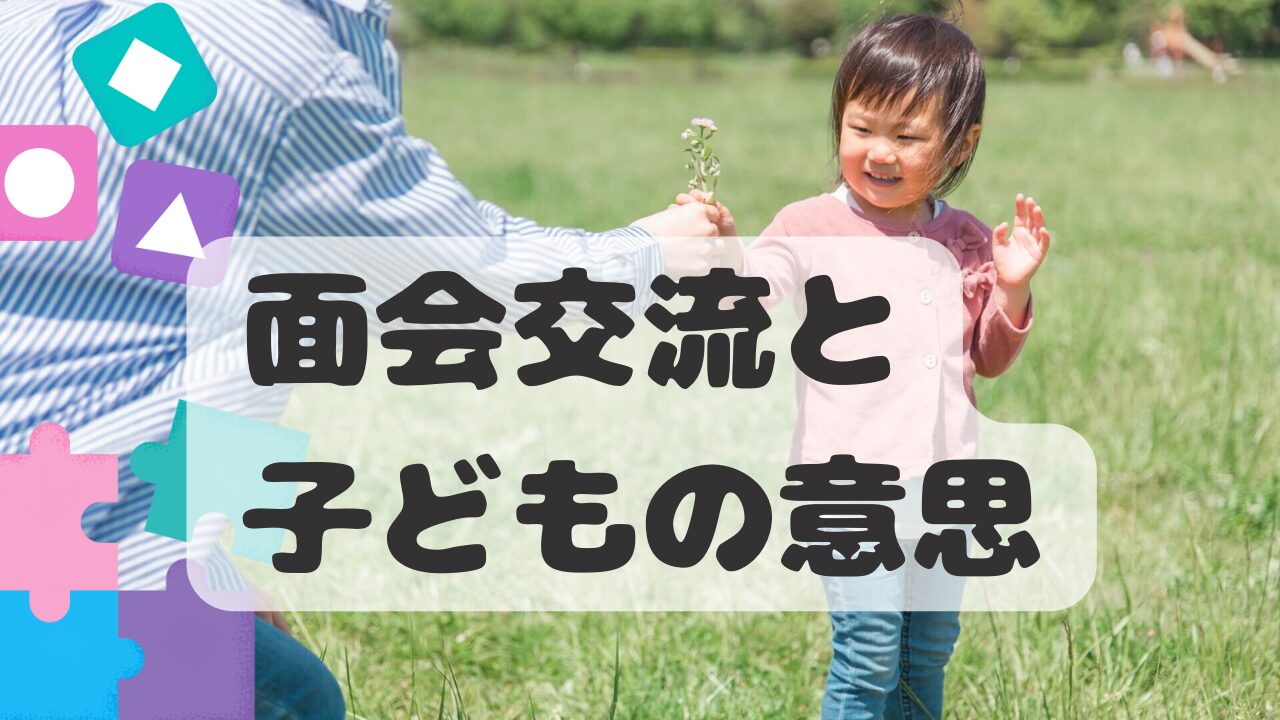
【面会交流】面会交流において子どもの意思はどれくらい尊重される? | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…
親同士が面会交流することに合意していても,子どもがなかなか非監護側の親に会いたがらなかったりすることもしばしばあります。 今回は面会交流実施において,子どもの意…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


海外の共同親権は成功している?共同親権の問題点や日本の課題について解説します。 | DV・モラハラ・離婚…
2024年5月、離婚後も共同親権を選択することが可能とする改正民法が成立し、2026年までに施行されることになります。 一方、日本では、共同親権を導入することで、DVや虐待…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


子どもを叩く夫。これって虐待?子どもへの体罰や暴言を見逃してはいけない理由 | DV・モラハラ・離婚で弁…
配偶者からのDV・モラハラ被害に遭っている方の中には、第三者から見れば明らかなDV・モラハラにも関わらず「自分がDV・モラハラを受けているのか分からない」というケース…