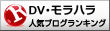DVモラハラ加害者が反省しない理由と治すのが難しい理由を弁護士が解説
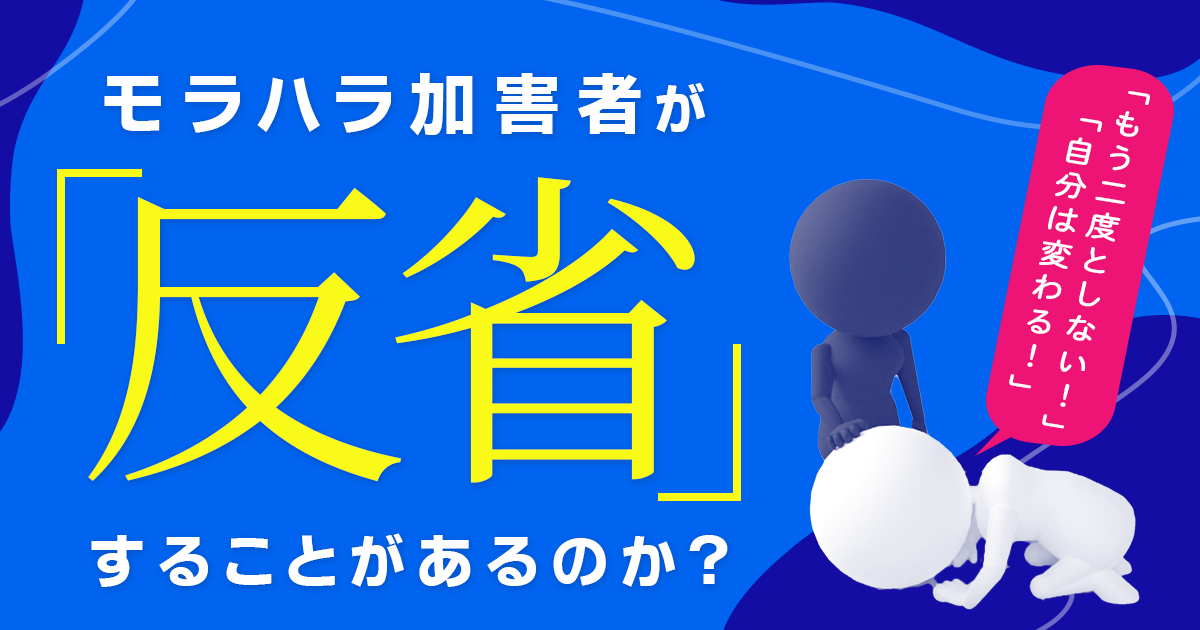
DVモラハラ加害者が謝罪して反省していると言っても、その言葉に本当に意味があるのでしょうか?
実は、DVモラハラ加害者が心から反省し、行動を改めることは非常に難しく、ほとんどの場合、期待しているような改善は見込めません。
加害者は反省しないことが多く、その原因は深い心理的な背景や自己中心的な思考にあります。また、治療が難しいのは、その根本的な問題が解消されることがほとんどないからです。
あなたが「変わってほしい」と願う気持ちは理解できますが、その期待に応えることができる可能性は低いのが現実です。
この記事では、DVモラハラ加害者が反省しない理由と、その治療がいかに難しいかについて、詳しく解説します。
加害者の言葉に惑わされず、あなた自身がどう行動すべきかを一緒に考えていきましょう。
目次
DVモラハラ加害者は自分を省みることができない
誰しも怒りを感じたとき、頭に血が上り、相手に傷つく言葉を発してしまうことがあります。
しかし、普通の人であれば、その後に「言い過ぎた」と反省したり、後悔したりするのが一般的です。
自分が犯した行動や言葉について、冷静に振り返ることができるからです。
しかし、DVやモラハラの加害者にはこの「後悔」や「反省」がありません。
自分の行動に対して一切の責任を感じず、常に自分が正しいと信じています。
そのため、自分の言動を省みることはなく、むしろ指摘されれば過剰に反応し、攻撃的になります。
さらには、議論をすり替え、話題を本来の問題から外し、被害者を悪者として仕立て上げることが常です。
とにかく「自分は悪くない、お前が悪い」とつ責任転嫁を図ります。
モラハラ加害者の行動は発達の未熟さから来ている?

DVモラハラ加害者の特徴の一つは、「すべてを他人のせいにする」「他者の世界や経験を否定する」といった傾向が見られることです。
これらの行動は、「自己中心性」と呼ばれる発達段階の未熟さから来ていると考えられます。
自己中心性とは
ピアジェという発達心理学者が提唱した概念。自分と他人を明確に区別できず、他者の視点を理解できない性質のこと。自分とは異なった視点があることを知らず、自分と同じ考えや価値観を相手を持っている(持つべきである)と思う。これは、前操作期(おおよそ2歳~7歳)といわれる発達段階にある子の特性です。
「自己中心性」とは、日常的に使われる「自己中(ジコチュー)」という言葉の意味とは少し異なります。
一般的な「自己中」は、他者の視点を理解しながらも、自己の利益や快適さを優先し、他人のことは気にしない状態を指します。
しかし、発達心理学で言う「自己中心性」は、子どもが他者の視点を理解できない段階で持っている特性であり、これは発達の過程で見られる自然なものです。
この「自己中心性」は、時間が経つにつれて克服され、子どもが他者の視点を理解し、自己中心的な考え方から脱却する過程(「脱中心化」)を経て、社会的に適応していきます。
一方で、モラハラ加害者は、育った環境や性格、そしてその人が経験した人生の中で、「脱中心化」の過程がうまく進んでいなかった可能性があります。
この結果、他者の意見や思い通りにいかない現実を受け入れられず、自己中心的な思考を強く持ち続け、成長してしまうことがあります。こうして、自分と他者の「境界」を認識できずに生き続けることになるのです。
思春期には、「理想と現実のギャップ」に悩みながら成長していきますが、モラハラ加害者はこの苦しみや葛藤を乗り越えず、自己中心的な世界観を維持するために、他者を支配し、自己を守る手段としてモラハラ行動に頼ることになるのです。
一見、社会ではうまくやっているように見える、外面がいい人もいるのはなぜか

モラハラ加害者の中には、職場やご近所づきあいでは感じの良い人に見える、いわゆる「外面がいい」タイプの人も多くいます。周囲の人からは「礼儀正しい」「仕事もできる」「家族思いに見える」と評価されていることも多く、被害者が相談しても「まさかあの人が?」と信じてもらえないことがあります。
ではなぜ、家庭内では別人のようにモラハラをしてくるのでしょうか?
それは、モラハラ加害者が“社会での自分”と“家庭での自分”を使い分けているからです。社会では、モラハラ加害者は「どう見られるか」を人一倍、過剰に気にしています。周囲に「良い人」「立派な人」と思われることに強くこだわっているため、外では必要以上に理性的に振る舞おうとします。
でも、心の奥では「自分が正しい」「思い通りにならないと気がすまない」といった未熟な考えを強く持ち続けています。そして、誰にも見られていない家庭という場で、その本性が現れるのです。
家庭内では、相手を思いやるのではなく、自分の不安やイライラをぶつけてしまいます。パートナーを支配し、コントロールすることで、自分の中の不安や葛藤を抑え込もうとするのです。
モラハラ加害者にとって、家庭は「思い通りに振る舞える場所」であり、パートナーはまるで“母親代わり”のように扱われます。
外では抑えていた不満や不安を、家庭では遠慮なくぶつけるのです。まるで3歳児が母親にわがままを言うように、未熟な甘え方で相手を支配しようとします。
つまり、家庭という空間は、加害者の未熟さや依存心がそのまま表れやすい場所なのです。
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

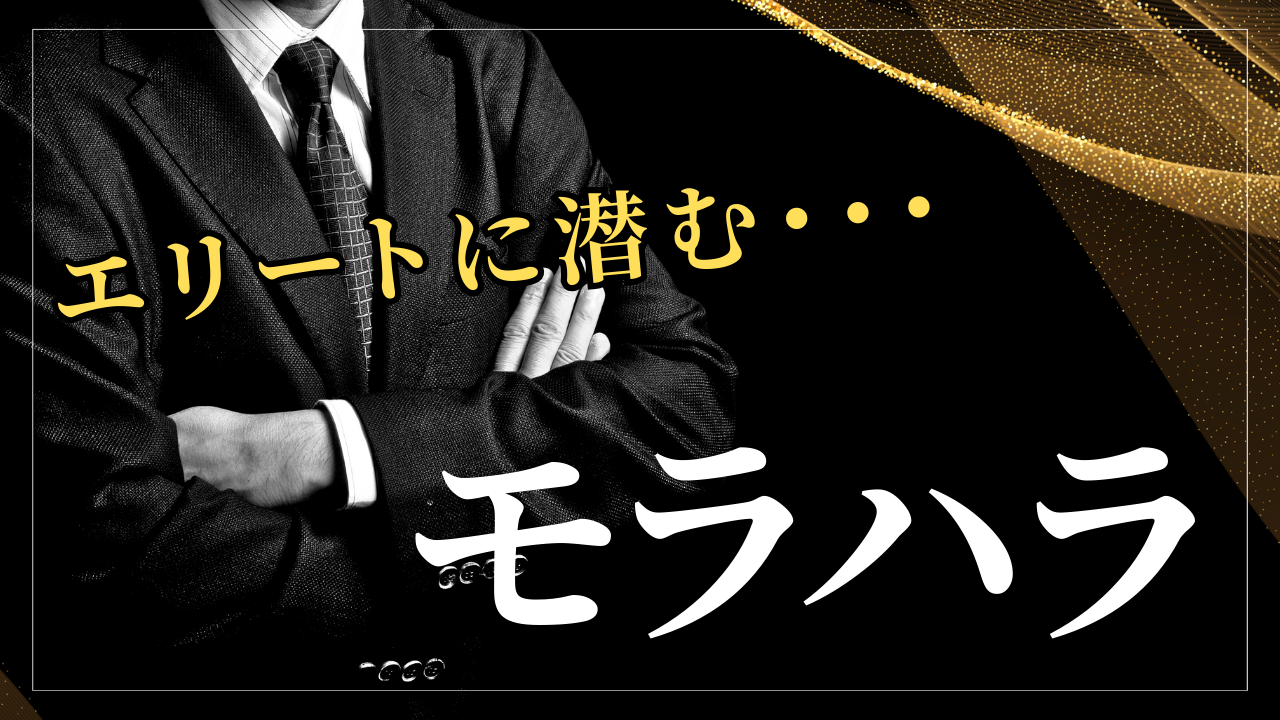
高学歴・高収入エリートモラハラ加害者に注意!社会的地位の高いモラハラ加害者は多い | DV・モラハラ・離…
「夫は外では完璧。でも家では私を傷つけてくる」──そんな違和感を抱えていませんか? モラハラ(モラルハラスメント)は、外面が良い人ほど、見抜かれにくく、周囲に理解…
DVモラハラ加害者の「二度としない」「反省している」は信じていいのか?

別れるというと「もう二度としない」とすがられる
モラハラ被害者が「離婚します」「出て行きます」と加害者に告げると、加害者は「もう二度としない」「俺が悪かった。反省する。」などと言って泣いてすがることがあります。
被害者は「本人も反省しているようだし、もう一度信じてみようかな…」と心が揺れてしまい、別れを決意できず、結局繰り返されるモラハラに苦しむことになります。
加害者の「反省」は簡単に信じてはいけない
被害者が「離婚したい」「出て行く」と言ったときに返される「もうやらない」は、本気の反省というよりも、その場を乗り切るための言葉であることが少なくありません。
自分にとって不都合な現実を回避するために、とりあえず口にしているだけという場合が多いのです。
DVモラハラ加害者は、なぜ相手が自分から離れたがっているのか、自分にどのような問題があるのかを根本的には理解していません。
彼らは、自分と向き合うつらさから逃げてきた人たちであり、今後も自分の問題に気づくことは難しいのです。
今まで変われるチャンスがいくらでもあったのに、変わらなかったから今の状態がある
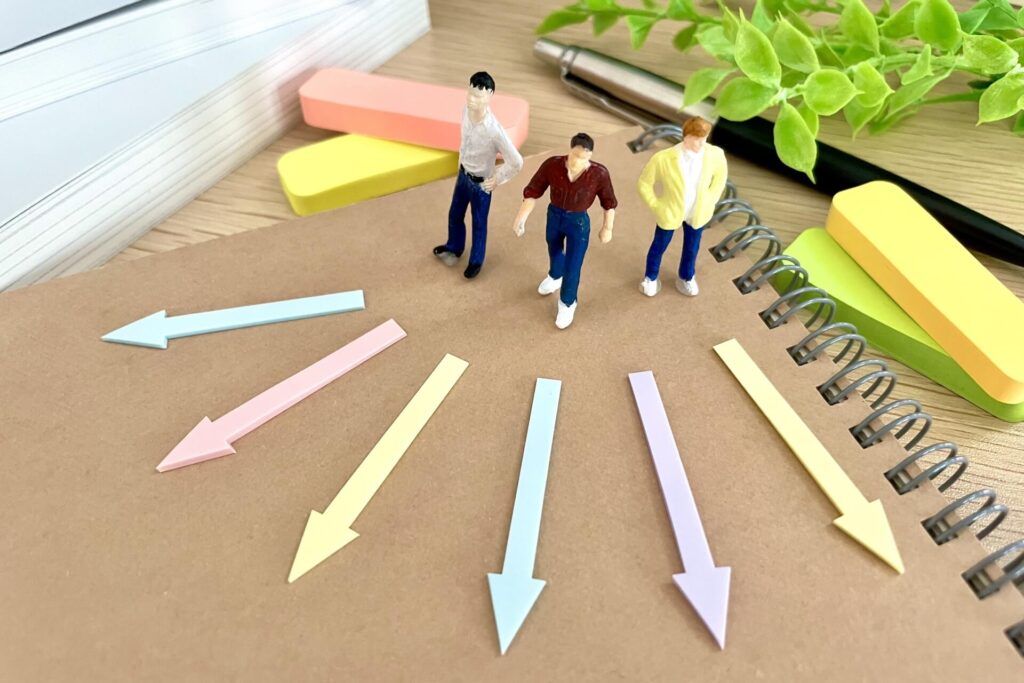
DVモラハラ加害者には、これまで何度も自分の問題に直面し、それを乗り越えて成長するチャンスがあったはずです。
しかし、加害者はその度に自分の心の問題から逃げ、被害者にその問題を押し付けて、心の安定を保とうとしてきました。
幼少期から染みついた葛藤の解決方法を変えることは、まるで新しい言語を学ぶように大変であり、そのためには長い時間と根気が必要だと言われています。
DVモラハラ加害者は、これまでその過程を避けてきたため、簡単に「俺は変わるから」と言っても信じることはできません。相手の言葉を鵜呑みにせず、行動をしっかりと観察し、見極めることが大切です。
なぜDVモラハラは改善することが難しいのか
DVモラハラは「底つき」しにくい依存症の一種である

加害者は、自分の中にある怒りや不安などのネガティブな感情を、そのまま認めることができません。そこで、自分の欠点や嫌な感情を、まるで相手が持っているかのようにすり替え、相手を批判します。

お前はいつもイライラしてるよな!本当に自己中心的だよな!!
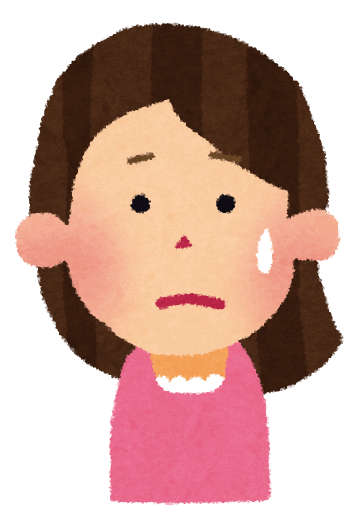
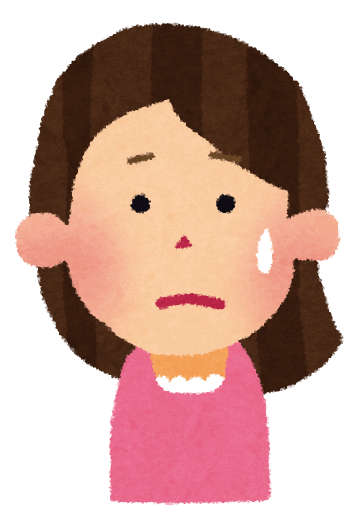
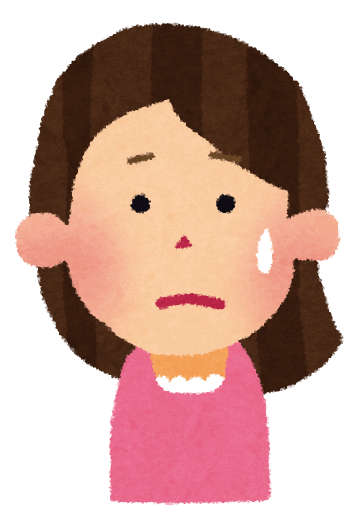
え、それ・・・あなたの自己紹介?
これは、自分の問題を相手に押しつけることで自分を守ろうとする「投影同一視」と呼ばれる防衛機制で、心理学者メラニー・クラインによって提唱されました。
この仕組みによって、加害者は自分の不安や苛立ちと向き合う必要がなくなり、一時的にストレスが解消されるため、「相手を攻撃する」という行動が脳にとって“快適な解決策”として刷り込まれていきます。結果としてこの行動は繰り返され、習慣化され、依存のようになっていきます。
DVやモラハラは、「ギャンブル依存」や「買い物依存」と同じく、「行為依存」の一種だと考えられます。
そして、このDVモラハラという依存行動の厄介な点は、アルコールや薬物のように健康を害することもなく、ギャンブルのように破産するリスクも少ないため、加害者自身に直接的なダメージがほとんど生じにくいということです。
代わりにダメージを受けるのは、常に被害者の側。
しかも、家庭という閉ざされた空間の中で繰り返されるため、周囲に気づかれにくく、加害者自身も「自分に問題がある」と気づく機会がほとんどありません。
依存症からの回復に必要とされる「底つき体験(人生がどうにもならなくなったと気づく瞬間)」が得られにくいのです。
しかも、支配関係の中で共依存となり、抜け出せなくなっている被害者が加害者のもとに留まり続けることで、加害者は「このままでも大丈夫」「問題は自分ではなく相手だ」と思い込み、DVモラハラ行為がますます強化されていきます。
加害者の元に居続けることは、アルコール依存症の人の前に常にお酒があるのと同じ
DVモラハラ加害者には「行為依存」があることに加え、被害者との間に「共依存」という関係性も生まれています。
共依存とは、お互いに相手なしではいられなくなってしまう関係で、「私にはこの人しかいない」「私が支えなければ」という思いから、被害者は辛くても相手から離れられなくなります。
しかし、このような状況は、アルコール依存症の人の前に常にお酒を置いているのと同じです。たとえ加害者が「DVモラハラをやめる」と決意し、一時的に優しくなる(ハネムーン期)ことがあっても、被害者が目の前に居続ける限り、DVモラハラという依存行動を断ち切るのは非常に難しくなります。
そして加害者は、やがて「やめられない自分」を正当化しようとし、「お前が悪いんだ」「俺はそんなつもりじゃなかった」「そもそも怒らせる方が悪い」と、被害者に責任を押しつけるようになります。こうしてDVモラハラはさらに悪化していきます。
依存症という視点からでも、DVモラハラをやめるということがいかに難しいことかわかります。
加害者から「もうしない、反省している」「変わるからチャンスをくれ」と言われたときには、再びモラハラを始める可能性があることを忘れずに、長い時間を待ち、つきあっていく覚悟があるかどうかを自分に問いかけてください。
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…




DVモラハラから抜け出せない共依存夫婦とは?特徴と心理、抜け出す方法について解説 | DV・モラハラ・離婚…
「DVやモラハラを受けていても、なかなか相手から離れることができない」そのような関係は「共依存」という「関係性の依存症」によるものかもしれません。このコラムでは、…
調停や裁判でのふるまいを見ても、自分の行動を省みる加害者は少ない
DVモラハラ加害者の特徴として、やたらと被害者ぶるところもあります。弁護士との話し合いの場で、突然泣き出されたこともあります。自分は家族、子供のことをいつも大切に思っていた。妻が家を出て行ったことなど信じられないと。。。
相談の時に依頼者の女性から聞いていた夫の態度とは全く違っていたため、戸惑いましたが、何度も交渉を重ねている内に本性を現します。
やはり、依頼者の言っているとおりの、自分のことしか考えないかなり自己中心的な人物であることが分かりました。その後は依頼者に対し、かなりの攻撃的な態度や嫌がらせと思われる態度を繰り返してきました。結局あのとき、泣いていたのも演技だったのです。


またあるときには、心療内科に通院し、妻が勝手に別居したせいで自分はこんなに精神的に苦しんでいると調停で訴えてきた人もいます。とにかく妻のせいで、精神的に落ち込み耐えられない、自分は被害者だ、、と。
このような加害者のふるまいを実際に見ていると、加害者は自分のことを省みることが出来ない人達だと感じます。人間は反省するからこそ、人間的にも成長すると思われるのですが、残念ながら加害者にはそういった要素は皆無に等しいです。
DVモラハラを改善できる可能性のある人はこんな人
これまで、DVやモラハラ加害者が変わることの難しさについて解説してきました。では、DVモラハラ加害者は絶対に改善の余地がないのでしょうか?
非常に難しいですが、DVモラハラを改善できる可能性のある人はいます。とはいえ、そのためにはいくつかの重要な条件が揃う必要があります。ここでは、改善の可能性がある人の特徴を具体的にご紹介します。
- モラハラ被害者以外の第三者に、「自分のモラハラを治したい」と正直に相談できている。
加害者が自分の行動に問題を認識し、改善する意志を示すことができるかが第一歩です。誰かに正直に自分の問題を話すことは非常に勇気が要りますが、この勇気を持つことが変化の第一歩になります。 - 「自分のモラハラは自分ひとりの力では治せない」と、自分の無力さを認めている。
加害者が自分だけで解決できるという誤った認識から解放されることが大切です。自分の限界を認め、外部の支援を求めることができるかどうかが、改善への鍵となります。 - モラハラを改善するために、カウンセリングや、加害者プログラム等の外部の機関に足を運ぶなど、実際に行動ができている。
言葉だけでなく、実際に行動を起こすことが非常に重要です。専門的な支援を受けることが、加害者が本当に変わるための一歩となります。 - 「自分のこれまでの生き方が間違っていた」「自分の価値観は間違っていた」と素直に認めることができている。
自分の行動や価値観を反省し、それを改善する意欲があることが、真の変化を促すきっかけとなります。自己認識と自己改革への強い意志が必要です。
自分が加害者だと認められるかが鍵
DVモラハラは病気ではなく、「自分の葛藤を他者に押しつけることに依存してきた生き方」の問題です。
そのため、病気のように「治る」とはいかないものの、意識的に「やめ続ける」ことは可能です。そのためには、本人の覚悟と、「加害者更生プログラム」などの支援機関の支援が重要となります。
DVモラハラ加害者が本当に後悔する時
DVモラハラ加害者が後悔を感じるのは、大切な人を失ったり、家庭が崩壊した後です。多くの加害者は「自分なりに家族を大切にしてきた」と感じており、その時は問題を深刻に捉えていませんでした。
しかし、状況が壊れた後、ようやく自分の価値観や行動が間違っていたことに気づきます(残念ながら気づかない人もいます)。
この気づきには大きな苦しみが伴いますが、これが変わるきっかけになることもあります。
後悔を無駄にせず、反省し、自己を振り返ることが成長への鍵となります。
加害者が自分と向き合い、行動に移すことができれば、その後の人生に大きな変化が訪れるでしょう。
まとめ


DVモラハラ加害者が改善するのは本当に難しいことです。
もし、加害者と一度は別れる決心をしたものの、「自分は変わるから」と相手にすがられ、決心が揺れ動いている方がいらっしゃったら、十分あるDVモラハラ再開の可能性に耐えられるか、相手が変わるまで、自分や大切なお子さんが加害者のストレスの受け皿になりつづけることに耐えられるかをよく見極めていただけたらと思います。
「離れる」決断は、加害者も被害者も成長するチャンスを与えてくれます。共依存から抜け出し、自分とお子さんの幸せを最優先にするための大きな一歩です。「もっと理解してあげられれば」「もっと支えてあげられれば」と罪悪感を感じる必要はありません。加害者が変わるかどうかはその人次第です。
最も大切なのは、あなたとお子さんを守ること。離れることで、新たな未来への道が開けます。
あなたとお子さんにとって最良の選択をしてくださいね。
参考文献
谷本恵美(2012)『カウンセラーが語る モラルハラスメント 人生を自分の手にとりもどすためにできること』 晶文社