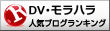モラハラ離婚後の元夫の嫌がらせから自分と子どもを守る方法
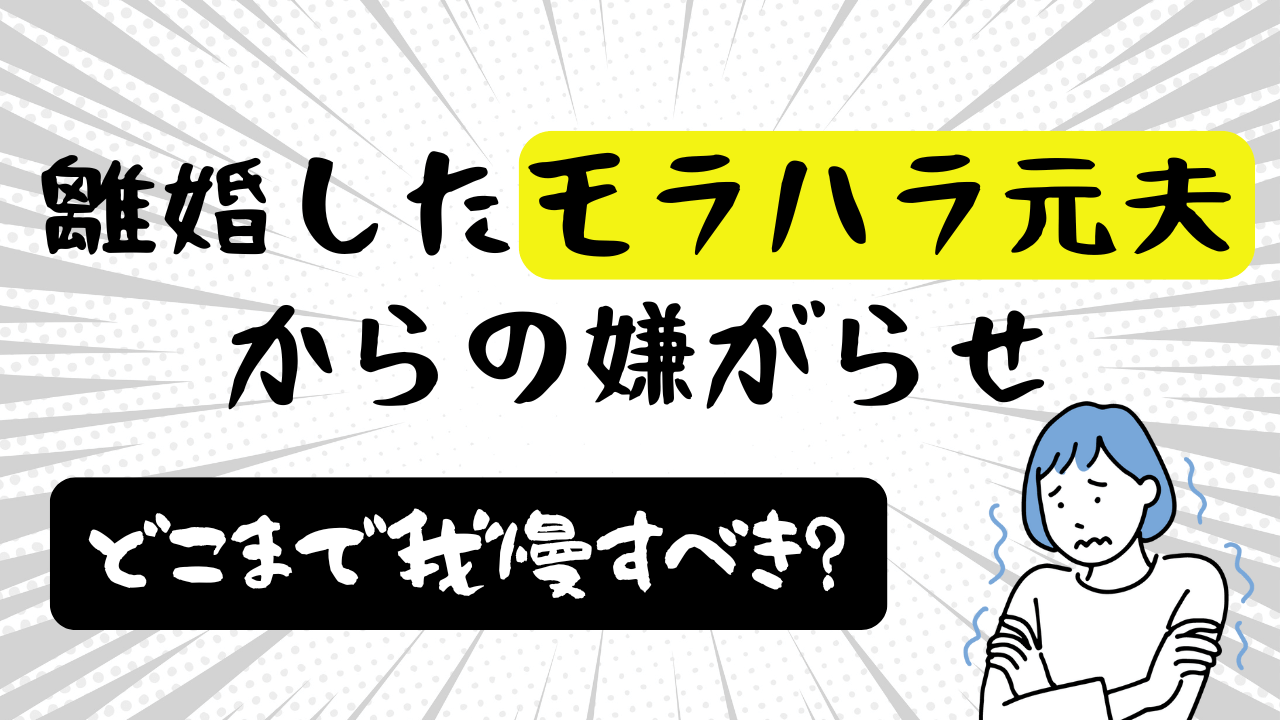
離婚後、元夫からLINEや電話、SNSでの連絡が続くと、「これは普通のやり取り?それとも嫌がらせ?」と迷ってしまうことがあります。
中にはモラハラやストーカー行為にあたる嫌がらせもあり、放置すると自分や子どもの安全に深刻な影響を与えることがあります。
この記事では、離婚後に元夫からの嫌がらせに悩む方に向けて、違法行為の見極め方や安全に対応する法的手段をわかりやすく解説します。
目次
離婚後の元夫の「通常の連絡」と「嫌がらせ」の境界

離婚後も、子どものことを確認するための連絡は「通常の連絡」です。
しかし、以下のような内容や頻度は、嫌がらせや犯罪に該当する場合があります。
注意すべき嫌がらせ例
- 「よりを戻したい」「あの時は許してくれ」など、あなたの意思を無視した連絡
- 「離婚したのはお前のせいだ」「お前の人生をめちゃくちゃにする」など、恨みや脅迫を含むメッセージ
- 家や職場への押しかけ、SNSでの執拗な監視
- 子どもを通して同情を引いたり、母親の悪口を言う
我慢してしまうと、元夫の支配が長引くリスクがあります。
法的手段①:ストーカー規制法で嫌がらせに対応

ストーカー規制法とは
ストーカー規制法は、つきまといや嫌がらせからあなたを守る法律です。
繰り返される行為は、刑事罰の対象になります。
ストーカー行為の具体例
- つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ・うろつき
- 自宅や職場の前で待ち伏せする
- 通勤・通学の後をつける
- 監視していると告げる行為
- 相手の行動や服装等をメールや電話等で告げる
- 「お前を監視しているからな」等と告げる
- 面会や交際の要求
- よりを戻すようしつこく要求する
- プレゼントを受け取るよう要求する
- 乱暴な言動
- 脅迫的な言葉「死ね・殺す・呪ってやる」を浴びせる
- 家の前でクラクションを執拗に鳴らしたり、大声を出す
- 無言電話、連続した電話・FAX・手紙・メール・SNSのメッセージ等
- 拒否しているにもかかわらず、何度も電話やメール、LINE等を送信してくる。
- 汚物等の送付
- 動物の死体を送りつける
- 家の前に汚物をまく
- 名誉を害する事項を伝える行為
- 名誉を傷つけるような文章(事実の有無にかかわらず)をネットなどで公開する
- 性的羞恥心を害する事項を伝える行為
- 電話や手紙等で卑猥な言葉を告げる
- 交際中に撮影した性的な画像をネットに公開する
- GPS機器等を用いて位置情報を取得したり、GPS機器を取り付ける行為
- 相手の持ち物に勝手にGPSを仕掛ける
- スマホアプリを用いて相手の位置情報を取得する
警察庁「ストーカー被害防止のためのポータルサイト」より
相談先・対応
- 相談先:最寄りの警察署
- 対応:警告・禁止命令、悪質な場合は逮捕も
- 刑罰例:
- ストーカー行為:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 禁止命令違反:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
法的手段②:保護命令で自分と子どもを守る

保護命令とは
保護命令はDV防止法に基づき裁判所が発令する命令です。
元配偶者や交際相手に対し、一定の行動を禁止できます。通常1年間有効です。
- 被害者への接近禁止
- つきまといや住居・勤務先への徘徊を禁止
- 電話やSNS禁止
- ストーカー行為にあたる連絡を禁止
- 子どもへの接近・連絡禁止
- 同居する未成年の子へのつきまといや連絡を禁止
- 親族への接近禁止
- 成年を含む親族へのつきまとい禁止
- 退去命令
- 同居住居から加害者を退去させ、近づくことを禁止(通常2か月、最長6か月まで延長可能)
内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」より
相談先・申立て先
- 相談先:地域の配偶者暴力相談センター(#8008)や警察(申立て前に相談記録が必要)
- 申立て先:加害者住所・申立人住所・暴力発生地を管轄する地方裁判所
違反した場合
保護命令違反:逮捕の可能性あり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
発令状況(2022年)
2022年に終局した配偶者暴力等に関する保護命令事件は1,453件、そのうち保護命令が発令された件数は1,111件です。
また、保護命令発令の内訳は以下となっています。

法的手段をとるときの注意点

- 記録を残す:日時・内容・スクリーンショット・心理的被害も記録
- 周囲に相談する:信頼できる家族・友人・弁護士に状況を共有
- 自分の安全を優先する:無理に自分でやり取りせず、警察や弁護士を通じて対応
- 相談先を把握しておく:警察、弁護士、自治体の相談窓口を事前に知っておく
まとめ:我慢せず、自分を守ることが第一

離婚後も元夫からの嫌がらせに悩む方は少なくありません。
「関係を続けなければ」と無理に我慢すると、支配が長引くリスクがあります。
- 嫌がらせやつきまといは我慢する必要なし
- 支配や圧力の線引きを自分で意識
- 記録は法的手段で役立つ
- 状況が深刻なら警察や弁護士に相談
あなたには、暴力や嫌がらせを受けず、安心して生活できる権利があります。
小さな違和感の段階で行動することが、自分や子どもの安全を守る第一歩です。
離婚後の生活や子どもを守るポイントについてはこちらの記事も参考になると思います
↓↓↓↓
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


親が離婚した子どもの気持ちは?親が今日からできる心のケアと安心の作り方 | DV・モラハラ・離婚で弁護士…
離婚が最善の選択だと思ったけれど、子どもを傷つけてしまったかもしれない…と不安に感じていませんか?確かに、離婚は子どもにとって生活環境の変化やストレスを伴う出来…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

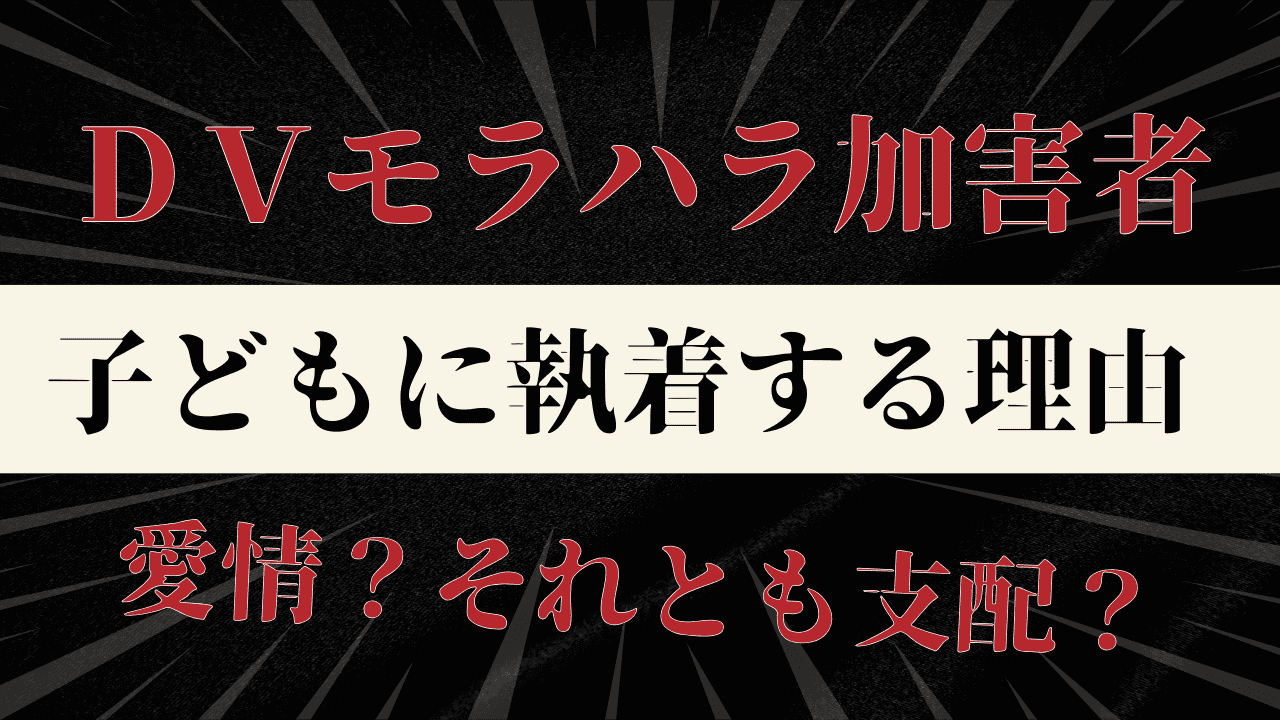
DV・モラハラ夫が親権や面会交流権を欲しがる理由と母子を守る安全対策 | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお…
離婚や別居後、これまで子育てを相手に丸投げしていたDV・モラハラ加害者が、突然「親権を取りたい」「面会交流をしたい」と強く主張してくるケースは少なくありません。 …
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

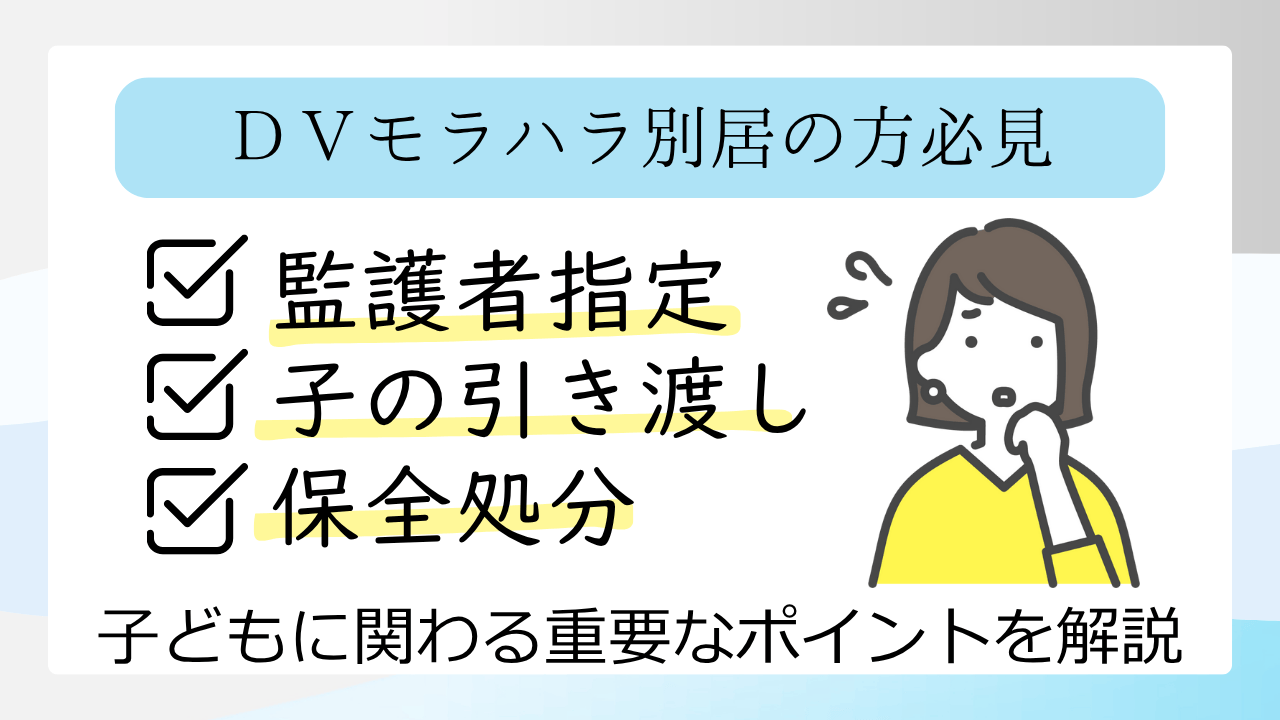
監護者指定・子の引き渡し・保全処分とは?子連れ別居で相手に申し立てられた場合の流れや対処法について |…
DVやモラハラから逃れて、やっとの思いで別居した方。しかし、別居後に「連れ去りは違法だ」「子どもは返さなければいけない」と相手方が主張する場合、「監護者指定」や「…