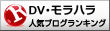親が離婚した子どもの気持ちは?親が今日からできる心のケアと安心の作り方

離婚が最善の選択だと思ったけれど、子どもを傷つけてしまったかもしれない…と不安に感じていませんか?
確かに、離婚は子どもにとって生活環境の変化やストレスを伴う出来事です。
でも安心してください。
子どもは、安心して暮らせる環境があれば、少しずつ心を回復していけます。
この記事では、離婚後の子どもの心の変化や、親ができる具体的なサポート方法、専門家や地域の支援の活用法をわかりやすく解説します。
目次
離婚後の子どもに起こる心理的変化

子どもが感じる不安や孤独
離婚は子どもにとって大きな生活の変化です。
「自分のせいで親が離婚したのでは…?」
「片方の親がいなくて寂しい」
「これからの生活はどうなるの?」
そんな不安や孤独を抱えることがあります。
子どもは表に出さなくても、胸の中で心配や罪悪感を抱えていることが多いのです。
法務省調査から見える感情の傾向
法務省の調査(2021年)によると、未成年時に親の別居・離婚を経験した子どもの感情は次の通りです。
- 悲しかった:37.4%
- ショックだった:29.9%
- 将来に不安を感じた:16.1%
- ホッとした:14.3%
- 経済的な不安を感じた:11.2%
- 状況が変わることが嬉しかった:11.0%
法務省:未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査 【簡易版】より
離婚は子どもに心理的負荷を与える一方で、場合によっては安心や安堵をもたらすこともあるのです。
特にDV・モラハラがあった場合、「安心できる生活になってホッとした」という声も少なくありません。
ACE(逆境的小児期体験)とは

ACEスコアと将来リスク
ACE(Adverse Childhood Experiences:逆境的小児期体験)とは、18歳までに経験する虐待(面前DV含む)・ネグレクト・家庭の不和などのストレス体験を指します。
ACEスコアが高いほど、成人後の心身の健康リスクが高まることが研究で明らかになっています。
10項目のストレス体験のうち、4つ以上体験した人は、0の人と比べて以下のリスクがあります。
- 年に2週間以上の抑うつ:4.6倍
- 自殺企図:12.2倍
- アルコール依存症:7.4倍
- 違法薬物の使用:4.7倍
- 薬物の注射:10.3倍
- 50人以上の性交経験:3.2倍
離婚とACEの関係
心理学研究では、離婚そのものよりも親の対立の有無が子どもの心に大きく影響することが示されています(Kelly, 1993)。親同士の争いが少なく、穏やかな環境であれば、離婚していても精神的に安定した子どもに育ちやすく、逆に離婚していないが親同士の争いが激しい家庭の子どもよりも、心の安定が保たれる傾向があります。
つまり、離婚は子どもにとって必ずしもネガティブな出来事ではなく、家庭内の平穏と親の冷静な対応が、子どもの回復や安定には何よりも重要なのです。
子どもに罪悪感を抱かせないために親ができること
「自分のせいで子どもに傷を与えてしまった」と悩む親は多いですが、子どもにとって最も大切なのは「安心できる環境」です。
両親がそろっていることよりも、安心して暮らせることの方が子どもの心を支えます。
片方の親がいなくても、祖父母・親戚・地域の人・先生・信頼できる大人とのつながりがあれば、子どもは「自分は大切にされている」と感じられます。
この「大切にされている感覚」が、レジリエンスを育む土台になります。
離婚後に子どもの心を癒やすためには

子どものレジリエンスを高める
レジリエンスとは、逆境から立ち直る力・困難を乗り越えて回復する力のことです。
子どもは本来この力を持っており、安心できる環境や信頼できる大人とのつながりによってさらに強く育ちます。
レジリエンスを育てる4つの要素
ポジティブ心理学の第一人者イローナ・ボニウェル博士は、レジリエンスを高める要素として、以下の4つを提唱しました。
- I have(支えがある):困ったときに助けてくれる人がいる
- I am(自分には強みがある):自分の良いところを理解している
- I can(困難を乗り越えられる):試練を乗り越える力があると信じられる
- I like(好きなこと・楽しいことがある):興味や楽しみを感じられることがある
親だけでなく地域や周囲の大人から支えを受けることも、子どもの心の強さを育てる大切な要素です。
2. 肯定的な体験を増やす
- 一緒に遊ぶ、笑う、褒める
- 子どもが興味を持つこと、好きなことを応援する
- 学校や地域の活動で小さな成功体験を積む
- 親以外の大人や友達と安心できる関係を築く
専門家や地域の支援を活用する
心理士やカウンセラーに相談することで、子どもが安心して気持ちを表現できる環境を整えることができます。
また、地域には子ども食堂やひとり親支援団体、子どもの居場所を提供するNPOなど、さまざまなサポートがあります。
これらは食料や生活の支援だけでなく、親と子が安心して人とつながれる場所にもなり、孤立を防ぎます。
さらに、ひとり親家庭を対象にしたイベントやレジャー活動も行われており、子どもが「楽しい」「安心できる」と感じられる経験を重ねることができます。
子どもの感情を受け止める
安心できる環境になると、子どもは抑えていた感情を爆発させることがあります。
泣いたり怒ったりするのは回復のプロセスで、悪いことではありません。
ただし「感情を受け止めること」と「行動を許すこと」は別です。
- 怒りや涙などの感情は受け入れる
- 物を壊す・人を傷つける・暴言を吐くことは許さない
- 癇癪で欲求を通そうとする行動は受け入れない
DV・モラハラのある家庭では「怒り=破壊や加害」と誤って学習していることがあります。
だからこそ「怒りは悪い感情ではなく、安全に表現できるもの」と伝えることが大切です。
癇癪を一人で対処することが難しいときは、一人で抱え込まず専門家の力を借りましょう。
まずは親自身が自分を癒やすこと

子どもを支えたい気持ちがあっても、まずは親自身の心が少しずつ回復していくことが大切です。
親が安心している姿を見せられることこそが、子どもにとって一番の安心材料になります。
- 子どもに支えてもらおうとしないこと
親の気持ちを子どもに背負わせてしまうと、子どもはさらに負担を感じてしまいます。 - 外部に気持ちを吐き出せる場をつくること
自分のDV・モラハラ被害を安心して話せる相手や場所を持ちましょう。子どもに別居親の悪口を話すのではなく、専門家や支援団体に思いを共有することが大切です。 - ひとりで抱え込まず、サポートを受け入れること
支援団体、カウンセラー、子育て支援など外部の助けを積極的に取り入れることで、親自身が楽になり、その安心感が子どもにも伝わります。
日常でできる「声かけ」と「小さな習慣」

声かけ例
- 「あなたがいてくれて嬉しいよ」
- 「今日はどんなことが楽しかった?」
- 「泣いてもいいよ。そばにいるからね」
- 「大丈夫、失敗してもまたやり直せるよ」
小さな習慣
- 寝る前に「今日一番楽しかったこと」を一緒に振り返る
- お弁当やおやつに子どもの好きなものを1つ入れる
- 週に1回は一緒に遊ぶ・散歩する時間を作る
- 子どもが話しかけてきたときは手を止めて向き合う
こうした積み重ねが、子どもに「自分は愛されている」「大切にされている」という確かな感覚を育てます。
まとめ:子どもの未来を一人で抱えこまない

- 離婚は心理的ストレスを与えるが、安全確保の手段になる
- レジリエンスは必ず育てられる
- 地域や信頼できる大人とのつながりが子どもの支えになる
- 親自身も外部の助けを借りて安心感を持つことが、子どもの回復につながる
子どもの心と未来は、あなた一人で抱えこむ必要はありません。
信頼できる大人や専門家、地域のサポートを活用しながら、子どもと一緒に少しずつ前に進むことが大切です。
参考文献
ランディ・バンクロフト著(2006)『DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒やす』明石書店
Kelly, J. (1993). Current Research on Children’s Postdivorce Adjustment. Family and Conciliation Courts Review, 31(1), 29–49.
子どもの心のケアや、離婚後の関わり方について理解を深めたい人は、こちらの記事も参考になると思います。
↓↓↓↓
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


「面前DV」を受けて育った子どもはどうなる?面前DVの定義と子どもへの影響 | DV・モラハラ・離婚で弁護士…
配偶者が日常的に子どもの前で私を罵倒したり、暴力を振るっていたけれど子どもに良くない影響を与えていたのではないか・・・ このように、子どもに直接暴力や暴言を振る…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

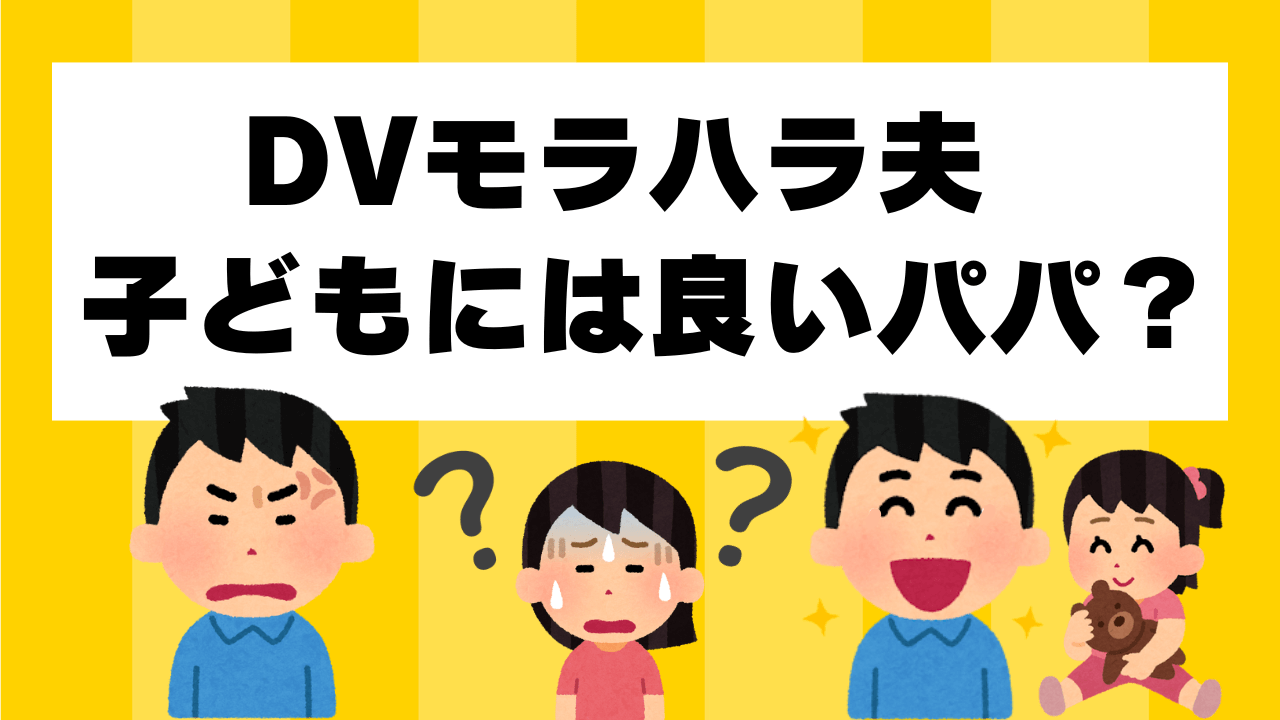
DVモラハラ親でも子どもは「パパ大好き」?「子どもには良い親」の理由と面前DVの危険性 | DV・モラハラ・…
自分には気に入らないと暴力を振るったり、暴言を吐く夫や妻。だけど子どもには甘すぎるほど優しい。結婚生活が辛く、離婚を考えるけれども子どもが「パパ(ママ)大好き」…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…


【モラハラ】問題のある非監護親との面会交流は認められる?【DV】 | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探し…
元夫(元妻)からのDVやモラハラが原因で離婚された方は「元夫の暴言暴力が怖いから,離婚後の面会交流はあまりさせたくない・・・」「面会中に子どもに暴言を吐いてトラブ…