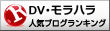監護者指定・子の引き渡し・保全処分とは?子連れ別居で相手に申し立てられた場合の流れや対処法について
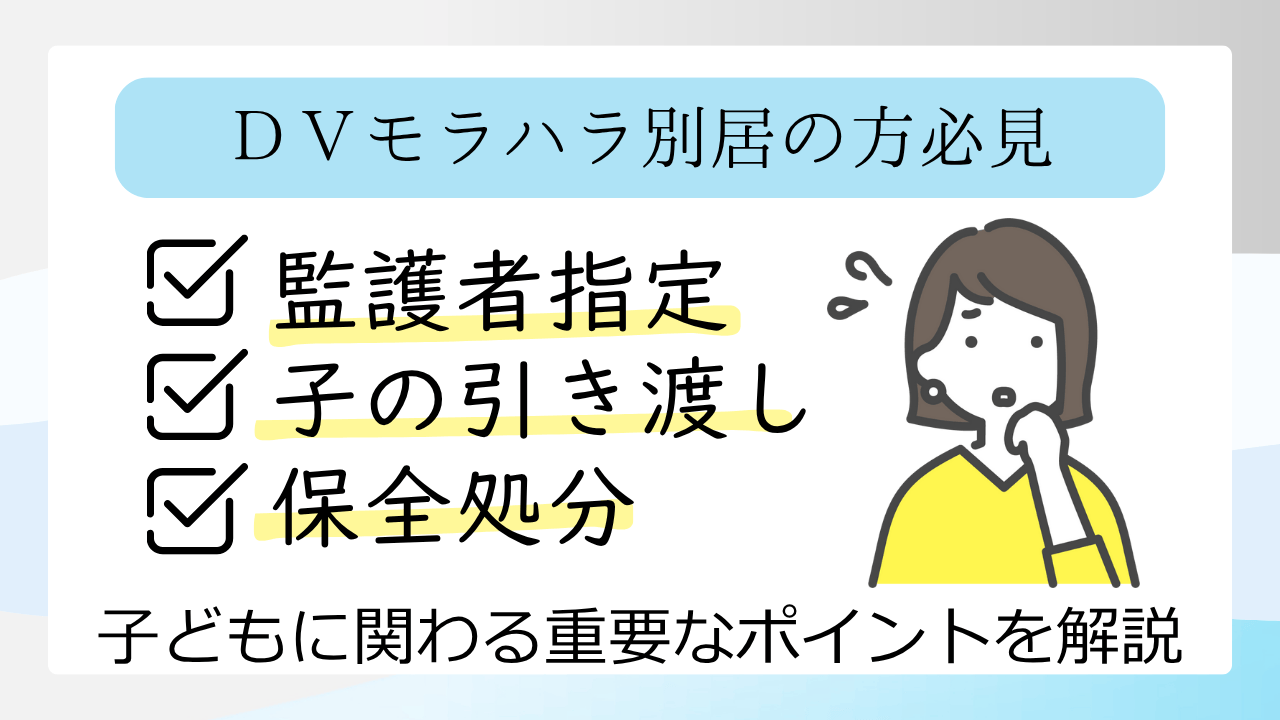
DVやモラハラから逃れて、やっとの思いで別居した方。
しかし、別居後に「連れ去りは違法だ」「子どもは返さなければいけない」と相手方が主張する場合、「監護者指定」や「子の引き渡し」、「保全処分」といった家庭裁判所への申し立てがされる場合があります。
監護者指定とは、「別居中、子どもはどちらの親が育てるか」について決める手続きです。裁判所は監護状況や子どもの意向を丁寧に調査し、公正に判断します。
監護者として指定されるためには、自分が監護者として適していることを示す的確な資料や陳述書を提出することが非常に重要です。
この記事では、これからの手続きの流れや必要な準備、注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 監護者指定・子の引き渡し・保全処分の意味と違い
- DVやモラハラ別居後に起こりやすい法的トラブル
- 申立てが届いたときの対応方法
- 裁判所が重視する証拠と準備のポイント
- 弁護士に相談すべき理由と選び方
目次
監護者指定・子の引き渡し・保全処分の意味とそれぞれの概要

別居の際、特にDVやモラハラなどの問題が絡む場合、子どもの監護権を巡る争いが起こることがあります。その中で、家庭裁判所に申し立てる重要な手続きが「監護者指定」「子の引き渡し」「保全処分」です。
これらの手続きは、DV・モラハラ被害によって別居した親が子どもを連れて逃げた場合、別居された側から申し立てがなされることが多く、その際は速やかかつ的確な対応が求められます。
監護者指定とは
監護者指定とは、別居中どちらの親が子どもを実際に育てるかを家庭裁判所が決定する手続きです。
子どもを連れて別居した親とは逆に、子どもと離れて暮らす側(別居された側)が申し立てを行うことが多く、裁判所に対して監護者としてふさわしいと認めてもらうことが必要になります。
子の引き渡しとは
子の引き渡しとは、子どもを一方の親が無断で連れ去った、または正当な理由なく別居後に子どもを引き渡さない場合に、子どもを元の監護者の元に戻すよう裁判所に求める手続きです。
別居された側が申し立てることが多く、DVやモラハラからの避難であっても「連れ去り」と主張されることがあります。しかし、裁判所は別居前後の監護状況等を総合的に判断し、子の福祉を最優先に考えます。そのため、正当な理由や証拠があれば、引き渡しは認められません。
保全処分とは
保全処分とは、正式な審判の判断が出る前に、子どもの安全や安定した生活を守るために、家庭裁判所に一時的な措置を求める手続きです。たとえば、子どもの引き渡しや監護者の指定についての審判は、申し立てから裁判所の決定が出るまでに多くは半年以上かかります。
しかし、その間に子どもの心身に悪影響が出るおそれがあるような場合には、審判の前に暫定的な措置が必要になることがあります。そこで、審判を待たずに、早期に裁判所の判断を得られる方法として「保全処分」が利用されます。
保全処分の手続きでは、審判に比べて比較的短期間で裁判所の判断が出されることが多く、子の安全性が害されるような場合等、緊急性が高い案件において重要な役割を果たします。
監護者指定・子の引き渡し・保全処分が相手から申し立てられたら

監護者指定・引き渡し・保全処分はセットで申し立てられることが多い
監護者指定や子の引き渡しの申立てがされた場合、多くのケースで保全処分(仮の措置)も併せて申し立てられます。
監護者指定や引き渡しの審判には半年以上かかることが多く、その間に子どもの安全や環境が脅かされるといった主張がある場合、「一刻も早く引き渡してほしい」という理由で、保全処分が利用されます。
保全処分が認められると、審判の結論を待たずに、子どもの仮引き渡しなどが命じられる場合があるため、非常に影響が大きい手続きです。
調停ではなく、審判から始まることが多い
家庭裁判所では原則として調停が先行しますが、監護者指定が争点となるケースでは、調停での解決は現実的ではないと判断されることが多く、最初から審判手続きで監護者の指定を求める申し立てがなされる場合が多いです。
相手から申し立てが届いたらどうする?
監護者指定や子の引き渡しの申立書が家庭裁判所から届いた場合、まずはその内容をしっかり確認することが大切です。
申立書の中には、相手側の申立の理由と趣旨が書かれており、「子どもを返してほしい」「監護者に指定されたい」といった要求が記載されています。中には事実と異なる内容や、こちらに不利な主張がされていることもあります。
ここで焦って、相手に直接アクションする等、単独で対応すると、裁判所に不利な心証を与えるおそれがあります。
まずは落ち着いて、相談できる弁護士を探し始めましょう。
監護者指定・子の引き渡し・保全処分は弁護士に依頼した方がよい
監護者の指定は、子どもの将来を大きく左右する重要な局面です。自分が監護者としてふさわしいことを、裁判所に納得してもらうには、主観的な訴えだけでなく、具体的で有効な証拠を提出し、説得力のある主張をする必要があります。
また保全処分が同時に申し立てられている場合には、短期間で裁判所の判断を促す必要があるため、スピードと法的な戦略性が極めて重要です。
これらの手続きでは、相手方から一方的な主張や、事実と異なる陳述書が提出されることもあります。特にDV・モラハラが絡む事案では、「子どもを連れて家を出たのは違法だ」といった主張がなされることが非常に多くあります。
一見もっともらしく聞こえる加害者の主張に対しては、DV・モラハラで避難せざるを得なかった実情を踏まえた説得力のある書面を作成し、子の福祉を中心とした判断を裁判所に促すことが不可欠です。
そのため、提出する主張書面には非常に精緻な構成が求められます。実際、50ページを超える書面が提出されることも珍しくなく、あわせて提出する証拠も膨大な量になることがあります。
これらの手続においては、
- 法的な論点を押さえた主張の組み立て
- 調査官対応へのアドバイス
- 必要な証拠の選別と提出
- 相手の主張への的確な反論
といった、専門的な視点と経験に基づいた、迅速かつ的確な対応ができる弁護士の関与が、結果を大きく左右することになります。
早い段階で信頼できる弁護士に相談し、適切な対応を始めることが大切です。
監護者指定・子の引き渡し・保全処分の具体的な流れ
STEP
相手が家庭裁判所に審判を申立てる
相手から家庭裁判所に対し、以下の申立てが同時に行われることが多いです。
- 監護者指定審判
- 子の引き渡し審判
- 審判前の保全処分(仮に子どもを引き渡すよう求める仮の措置)
申立てがされると、裁判所から申立書や証拠資料の写しとともに、第1回審判期日の呼出状が届きます。通常、申立てから2〜4週間程度に第1回期日が設定されます。
STEP
陳述書・資料提出の準備をする
裁判所から、審判の期日(話し合いや審理の日時)が通知されます。それまでに、陳述書、子どもと自分との関係性を示す資料を準備する必要があります。たとえば以下のようなものが求められます
- 現在の監護状況(別居前や別居後の監護状況、子の生活リズム、学校や保育園の状況などの陳述書)
- 別居に至った経緯(DVやモラハラがある場合はその証拠)
- 子どもにとって現在の生活が安定していることの証拠(支援してもらえる環境が整っているか等)
- 子どもとの関わりを示す写真や記録(育児の記録等)
- 相手が監護者として不適切であることを示す証拠(DVやモラハラ、不倫の証拠等)
弁護士に依頼している場合は、これらの資料から、弁護士が主張書面と証拠を作成します。
STEP
第1回審判期日
第1回期日では、裁判官が申立人・相手方それぞれから、現在の監護状況や別居に至った経緯などを確認します。
この段階では、以下のようなことが行われます。本人の体調や遠方の場合等の事情がある場合は、弁護士のみが出席します。
- 裁判官から双方への聞き取り(必要な場合)
- 提出書面の確認と今後の審理の方向性について
- 必要に応じて家庭裁判所調査官の調査指示
STEP
家庭裁判所調査官による調査
審判手続きにおいては、家庭裁判所調査官による調査が行われることが多くあります。裁判所の指示により、家庭裁判所調査官が双方の監護状況などを客観的に調査します。調査内容は以下のとおりです。
- 双方の住居環境、生活状況の確認(父母宅や祖父母宅、保育園、学校等に訪問し、面接)
- 子どもの日常生活や心身の健康状態
- 子どもの意向(年齢に応じて面談が行われる)
- 双方の監護能力や監護実績の比較
調査官は訪問調査や面談を行い、報告書として裁判所に提出します。この調査結果が、審判の判断材料として非常に重視されます。事前に弁護士と打ち合わせをして、対応のポイントを確認しておくと安心です。
STEP
第二回審判期日
審理の期間は約半年~程度で、必要に応じて複数回期日が設けられます。申立人・相手方双方は以下の資料を準備・提出します。
- 自分が監護者として適している理由を記した陳述書
- 子どもの生活実態を示す写真や生活記録
- DV・モラハラの証拠(診断書、LINE、音声など)
- 相手方の主張に対する反論資料
ここでは、単なる感情論ではなく、客観的な資料に基づいた説得力のある主張が求められます。
STEP
保全処分の判断
正式な審判の決定を待っていては、子どもの安全を確保できないと判断された場合、裁判所は仮に子の引き渡しを命じる「保全処分」を出すことがあります。
たとえば、DVや虐待の疑いがあり、現在の監護状況が子どもの心身に深刻な悪影響を及ぼすおそれがあると判断された場合などです。ただし、「急迫の危険」があるとまでは言えない場合には、保全処分は認められません。
保全処分の判断は比較的早く、申立てから数ヶ月程で決定が出されることもあります。ただし、あくまで仮の判断であるため、その結果が後の審判の決定と必ずしも一致するわけではないという点には注意が必要です。
STEP
審判の決定と不服申立て
家庭裁判所は、調査結果や書面をもとに審理を重ね、約半年~一年程度で監護者や引き渡しについて最終的な判断を下します。
審判書は郵送で届き、2週間以内に不服がなければ確定します。
子の引き渡しが命じられた場合は、速やかに子どもを引き渡さなければなりません。
引き渡しに応じない場合には、家庭裁判所の判断に基づき強制執行が行われる可能性があります。
不服がある場合には「即時抗告(そくじこうこく)」という手続きで上級審(高等裁判所)に判断を求めることができます。
裁判所が監護者を決める際の判断基準について
①主たる監護者は誰か
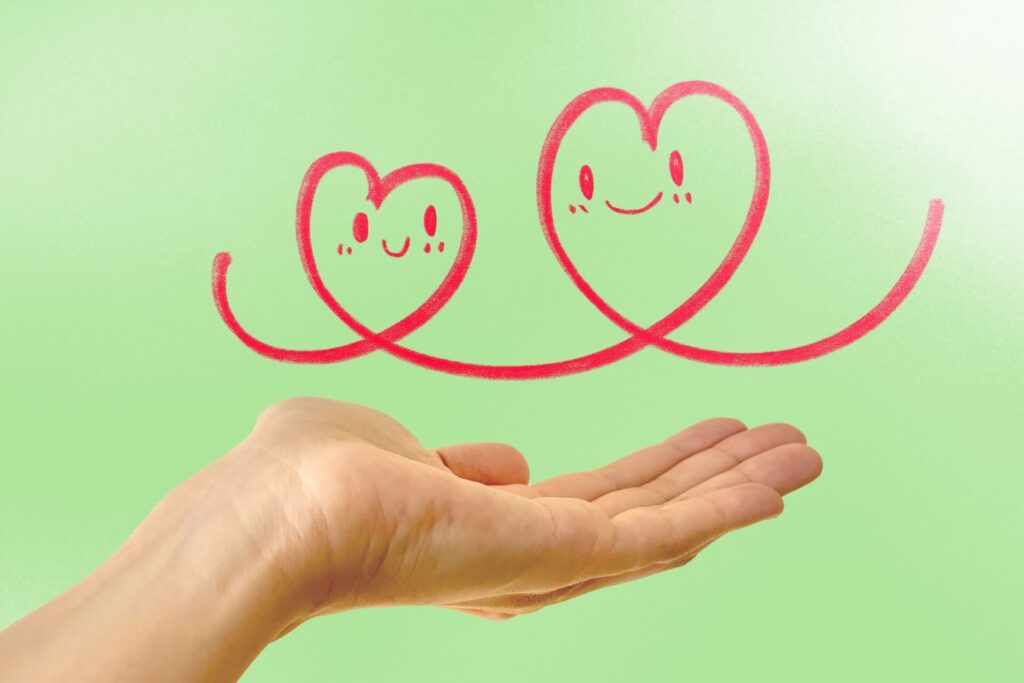
子どもが出生してから親権者の判断時点までの総合評価で、子どもの監護養育(子育て)を主に担ってきたと言える親を「主たる監護者」と呼びます。主たる監護者と子との間に形成された愛着関係や心理的絆は、離婚後も維持された方が子の福祉に沿うものと判断されることが多いです。
審判の際には、自分が今までどのくらい子育てに関わっており、現在の状況や、子育てをサポートしてくれる人はいるか、今後どのように養育体制を整えていくか等、陳述書という形で裁判所に提出します。
親権(監護権)は母親が有利?
「親権(監護権)は母親が有利」と言われることがあります。「母性優先の原則」という考え方です。それは日本の現状では、特に乳幼児期は主たる監護者が母親であり、子どもとの心理的身体的結びつきが母親の方が強い場合が殆どだからです。2022年の統計では、離婚後に母親が親権を取ったケースは88%、父親は12%でした。
一方、父親が主たる監護者としての役割を果たしており、今後の監護体制も十分だと認められれば、父親が親権(監護権)を取るケースもあります。
②監護の継続性

子どもの生活環境が変わることは、子どもに不安や混乱を招いてしまうので、現状の生活状況が安定している場合は、現状維持が子の利益の観点から望ましいという考え方が従前にはありました。しかし、この考え方は、「子どもを連れ去った先でも、監護状況が安定して継続されていれば監護者と認められることになる」として、子の奪い合いを助長しかねないという問題がありました。
現在では、監護の継続性は、子どもが幼い場合は「主たる監護者との精神的つながりの継続」が重要視され、就学後は、住居・学校・友人関係等の監護環境の継続性が重視されています。
③子の意思の尊重

子どもの年齢が高いほど、どちらの親と暮らしたいかという子どもの意思が親権者の判断において重要視されます。子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所が親権者を判断する際には子の陳述を聞かなければならないと法律で定められています。
実際には、おおむね10歳前後以上の子どもであれば子どもの意思が重視される傾向にあります。子どもの意向を確認する際には、家庭裁判所の調査官が子どもから話を聞くほか、心理テストや子の生活環境の調査等から総合的に判断されます。
④きょうだい不分離

きょうだいがいる事案では、一般的にきょうだい間の絆を損なわないよう、きょうだいを分離しないことが子の利益にかなうと考えられています。
しかし、長年きょうだいが別々に生活しており、その生活が安定している場合や、子どもの意思を尊重する場合は、きょうだいを分離することが認められるケースがあります。
⑤監護開始の態様について
別居後の離婚調停中に子を奪取したり、面会交流の機会に子どもを返さないといった行為は、「監護開始の態様」が悪質と判断されるおそれがあります。そのような場合、監護者としての適格性が疑われ、原状回復の観点から、子の引き渡しが命じられることもあります。
DV・モラハラからの避難による別居では、この「監護開始の態様」が争点となることが少なくありません。加害者側から「違法な連れ去り」と強く主張されるケースが非常に多いためです。
しかし、DV・モラハラからの避難であれば、「子どもを守るためにやむを得なかった行動」であることを丁寧に主張・立証していくことが大切です。たとえば、家庭内での暴言や暴力の記録、診断書、行政機関や警察への相談履歴などが、重要な証拠になります。
裁判所も、形式的には「連れ去り」に見える行動であっても、その背景事情を慎重に確認します。そして、子どもにとってどちらの親のもとがより安全で安定した環境かを重視して判断します。そのため、避難の理由が正当であること、そして避難後の生活が落ち着いており、適切に子どもを監護していることを証明することが重要です。
提出資料のポイント:裁判所が求める「説得力のある証拠」とは?
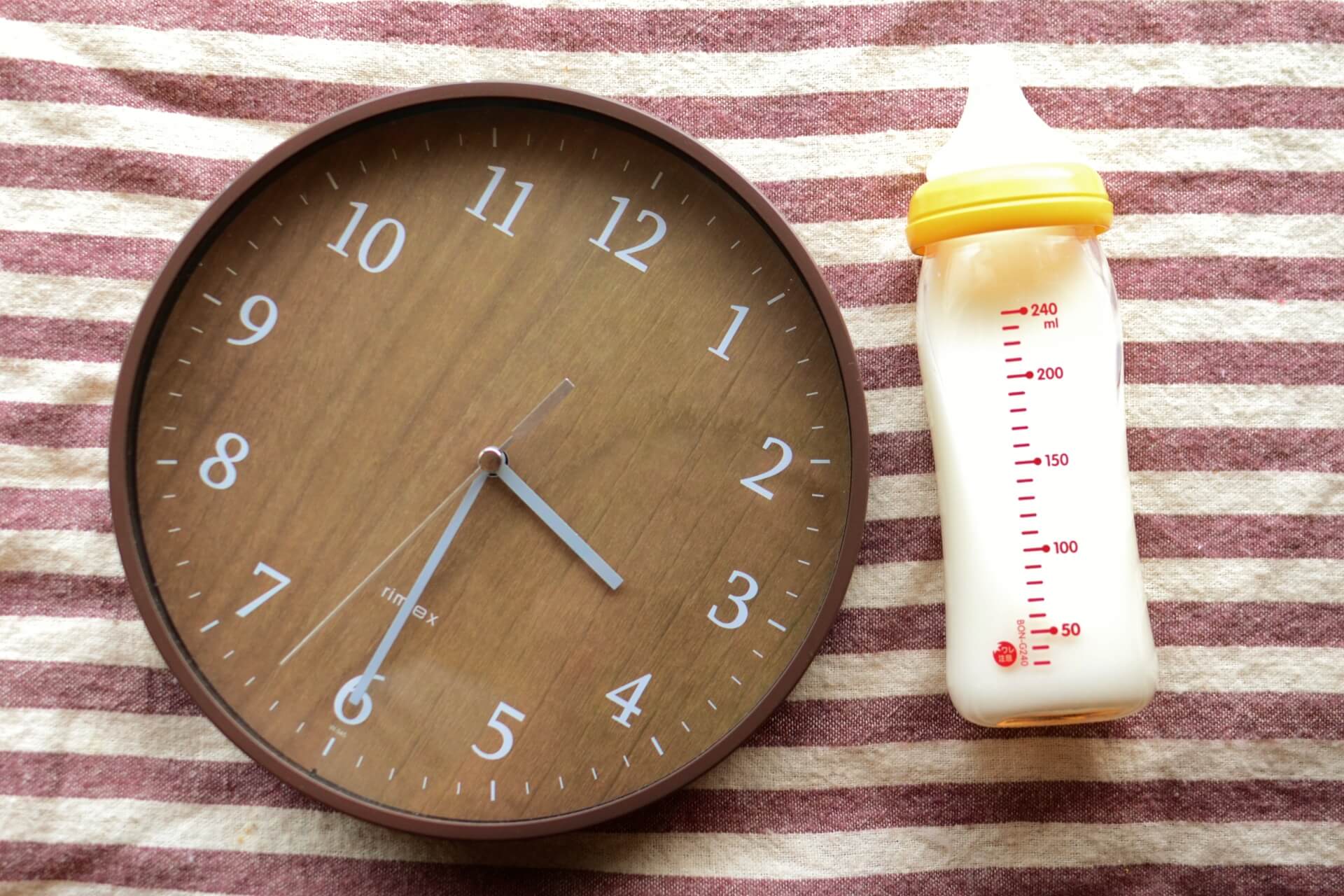
裁判所にとって重要なのは、「この人が監護者としてふさわしい」と納得できる具体的な資料や証拠です。主観的な感情だけでは判断されません。
以下は、実際に用意しておきたい資料の例です。弁護士が主張書面を作成する際には、依頼者から提出されたこうした資料をもとに構成していきます。そのため、できるだけ具体的かつ詳細な資料をそろえておくことが、非常に重要です。
子の監護に関する陳述書
別居に至った経緯や現在の子どもとの生活状況、監護者としての意志などを詳しく書く書面です。今後の生活設計(住居、就労、子どもとの時間など)についても具体的に書くことが重要です。
子どもとの生活を示す証拠
DVやモラハラが関係する監護者指定の審判では、相手方から事実とは異なる監護状況の主張がされることが少なくありません。
「相手は育児を全くしていなかった」とされる一方で、実際は主要な育児を担っていた──というように、双方の主張が大きく食い違うことがあるため、客観的な証拠で「誰が子どもの世話をしていたか」を示すことが非常に重要になります。
- 毎日の生活スケジュール(保育園・学校の送り迎え、食事、就寝など)
- 子どもとの日常の写真や育児日記(公園で遊ぶ、食事風景、病院受診時など)
- 連絡帳や保育園・学校の連絡資料、成績表や出席簿
- 子どもの健康管理の記録(予防接種、病院受診記録など)
相手方による不適切な行為の証拠(ある場合)
- 暴言・暴力の録音、録画データ
- LINEやメールなどのやり取り
- 医師の診断書(精神的被害やケガの記録など)
- 相談支援機関や警察への相談記録(配偶者暴力相談支援センターなど)
支援体制があることを示す資料
裁判所は、「ひとりで頑張ります」「子どもにさみしい思いはさせません」といった気持ちや努力目標ではなく、実際に子どもを安定して育てられる現実的な体制があるかどうかを重視します。つまり、支援体制についても客観的で具体的な裏付けが必要です。
- 実家や支援者からの協力を示す書面
- 保育園や学童などの受け入れ状況の証明
まとめ:早めの準備と弁護士選びが未来を守る鍵

監護者指定・子の引き渡し・保全処分は、子どもの生活や将来に大きく関わる非常に重要な手続きです。特にDVやモラハラが絡む場合、感情的な対立が激化しやすく、精神的にも負担が大きくなりがちです。
まずは冷静に状況を整理し、現在の生活や支援体制を客観的に示す資料を整えましょう。そのうえで、信頼できる弁護士と綿密に連携して対応していくことが不可欠です。
これらの手続きは専門性が高く、迅速性が求められるため、対応に慣れている弁護士は限られます。監護者指定や子の引き渡し・保全処分の実務経験の豊富な弁護士を慎重に選ぶことが、結果を左右する大きなポイントとなります。
早めの行動と適切なサポート体制の確保が、あなたとお子さんの未来を守る一歩になります。
つらい思いを抱え込まず、信頼できる専門家に相談することで、道が開けていきます。
離婚と子どものケアについてはこちらの記事も参考になると思います。
↓↓↓↓
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

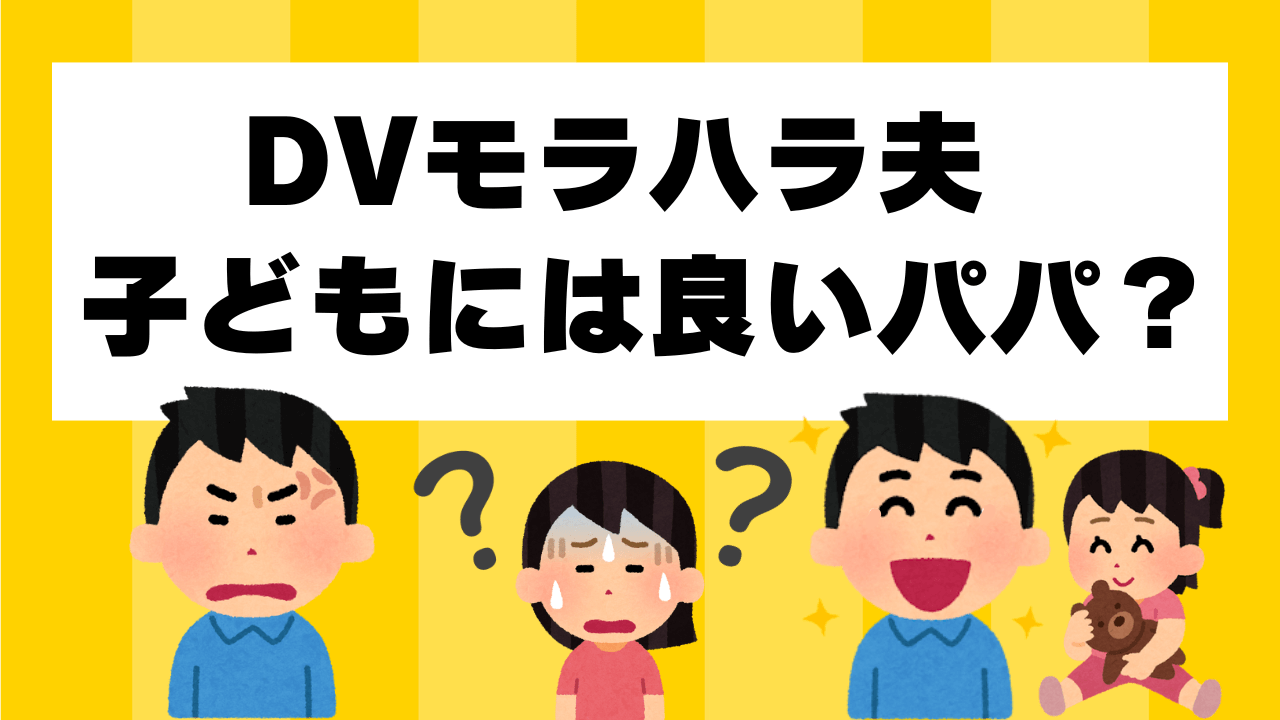
DVモラハラ親でも子どもは「パパ大好き」?「子どもには良い親」の理由と面前DVの危険性 | DV・モラハラ・…
自分には気に入らないと暴力を振るったり、暴言を吐く夫や妻。だけど子どもには甘すぎるほど優しい。結婚生活が辛く、離婚を考えるけれども子どもが「パパ(ママ)大好き」…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

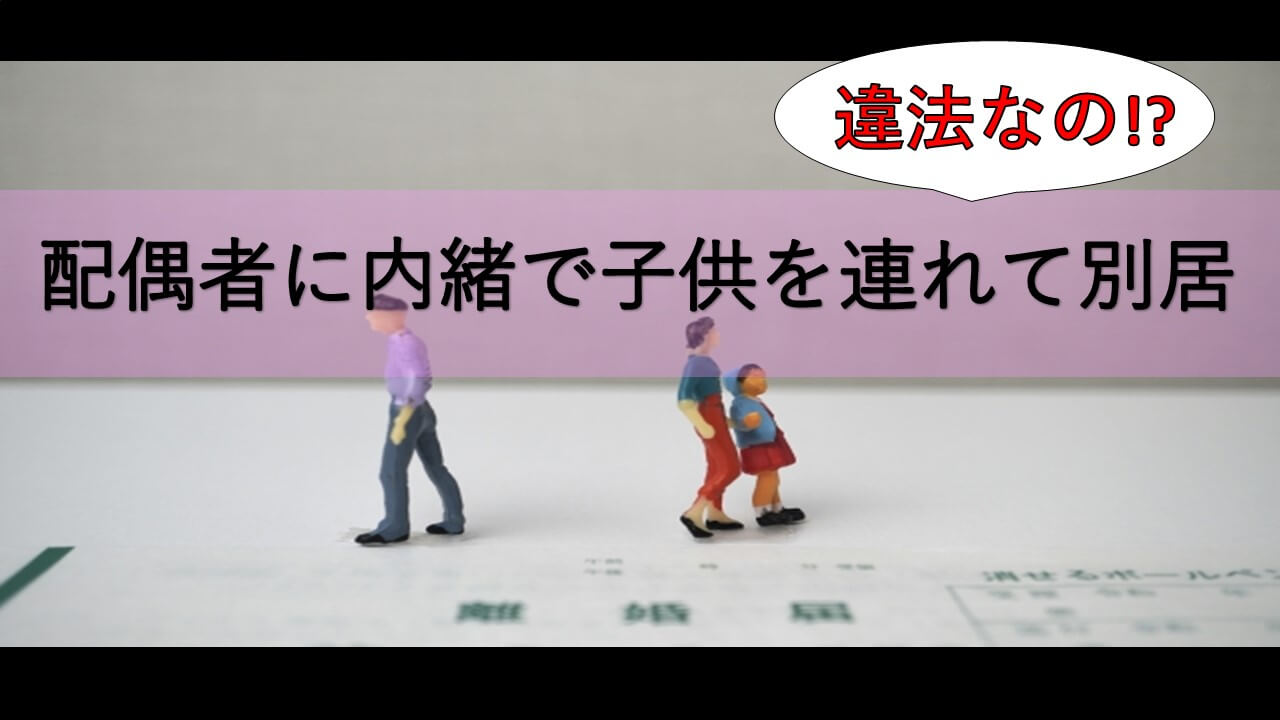
【子連れ別居】配偶者に内緒で,子どもを連れて別居することは違法? | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…
これはトラブルになるケースが非常に多いです。 そして,他方配偶者に内緒に,子を連れて別居をした場合に,他方配偶者から子の返還を求める裁判(監護者指定,子の引渡し…
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

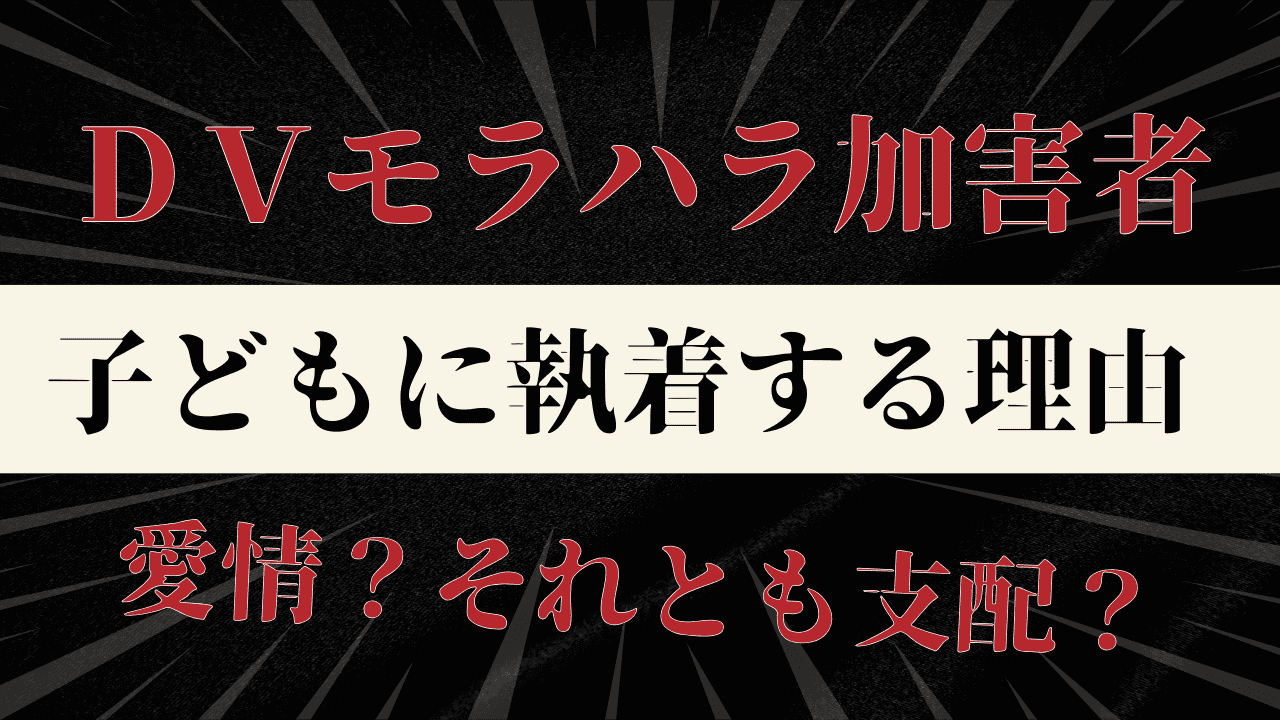
DV・モラハラ夫が親権や面会交流権を欲しがる理由と母子を守る安全対策 | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお…
離婚や別居後、これまで子育てを相手に丸投げしていたDV・モラハラ加害者が、突然「親権を取りたい」「面会交流をしたい」と強く主張してくるケースは少なくありません。 …