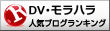離婚で退職金も分けられる?財産分与の計算方法と注意点を解説
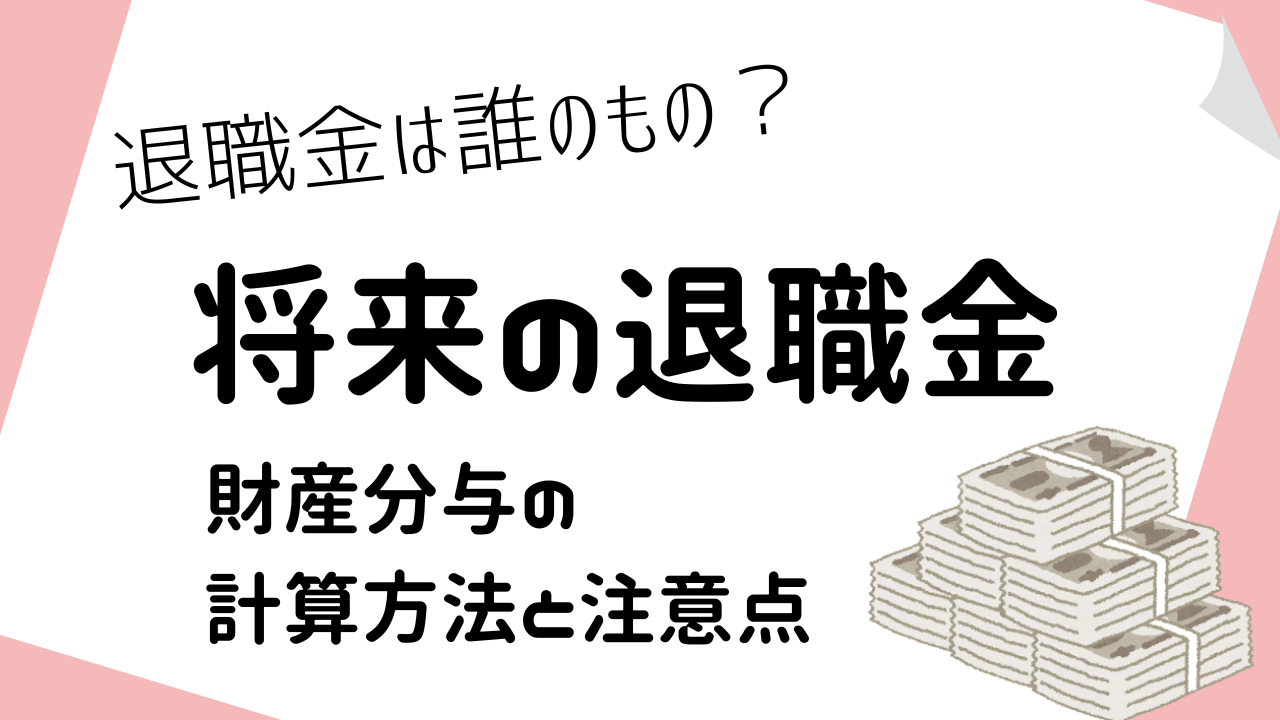
「退職金も分けるの?」と思った方へ
離婚のとき、「退職金も財産分与の対象になる」と聞いて驚く方は多いです。
「まだもらっていないお金なのに?」「会社のお金じゃないの?」と疑問に思う方も少なくありません。
実は、退職金も婚姻期間中に形成された部分は財産分与の対象となる場合があります。
この記事では、退職金が分与の対象になる条件や計算方法、注意点をわかりやすく解説します。
将来の生活に関わる大切なお金だから、正しい知識を押さえて安心しましょう。
目次
退職金は財産分与の対象になる?

離婚時の財産分与では、「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)」が対象です。
これには預貯金や不動産だけでなく、将来受け取る予定の退職金も含まれる場合があります。
財産分与の対象になるかの判断基準
- すでに退職しており、退職金の支給が確定している場合
→ 原則として財産分与の対象になります。 - 退職が近く、支給が現実的に見込まれている場合(数年以内など)
→ 裁判所でも分与対象とされる傾向にあります。 - 退職がかなり先で、支給が不確定な場合(例:30代の公務員など)
→10年以上支給が先の場合でも、分与対象とされる可能性があります。不確定要素が多い場合もあるので、個別の事案によって裁判所が判断することになります。
ポイントは「現実的に退職金が受け取れる可能性があるか」です。
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

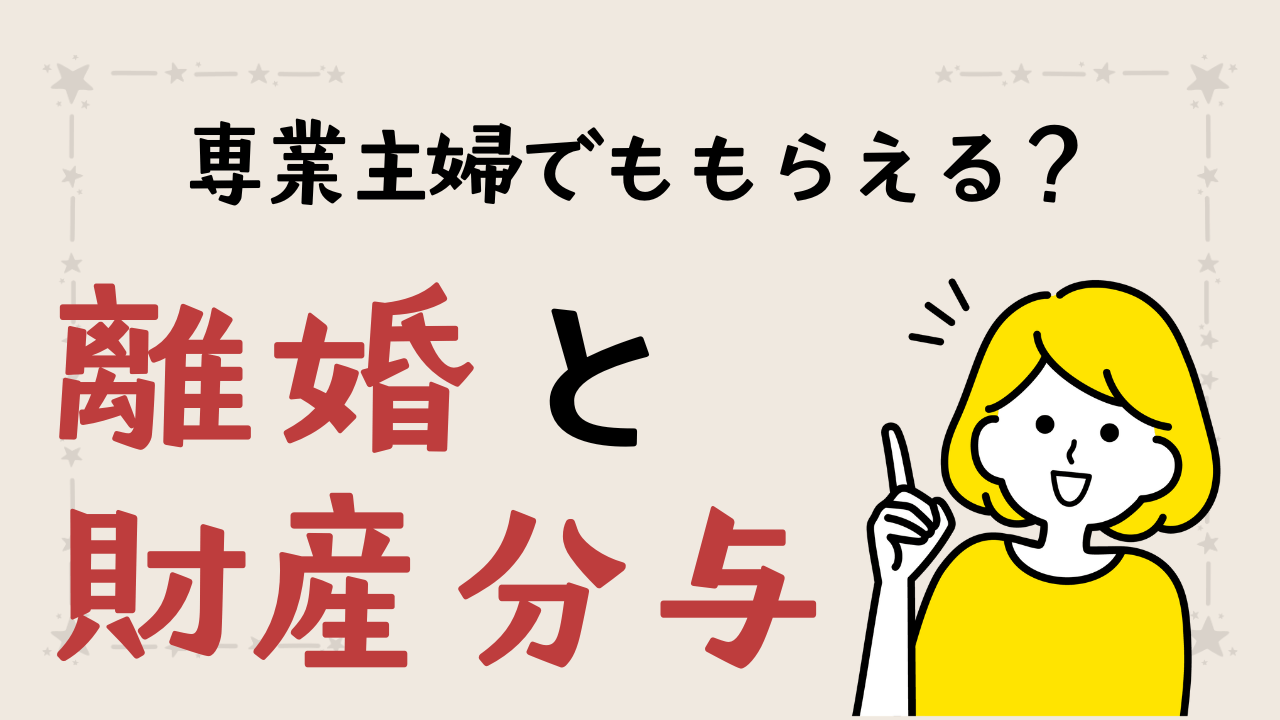
財産分与とは?専業主婦でももらえる“5つの財産”と注意点 | DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探しなら東京・…
離婚を考えたとき、多くの専業主婦が不安に感じるのが「財産分与」です。「夫名義の家でも私に取り分があるの?」「貯金や年金、退職金はどうなる?」といった疑問を持つ方…
退職金の計算方法【ケース別】

退職金全額が分与対象になるわけではありません。実務では婚姻期間中に形成された部分だけが対象です。
分与額の目安
分与額 = 退職金額 ×(婚姻期間 ÷ 勤続年数)× 寄与度(原則1/2)
①退職済みの場合
この場合は、実際に支払われた退職金の額をベースに分与額を算出します。
下記の例で考えてみます。
- 退職金額:2,000万円
- 勤続年数:40年
- 婚姻期間:20年
- 寄与度:1/2(夫婦の共同貢献とみなす)
分与額 = 退職金額 ×(婚姻期間 ÷ 勤続年数)× 寄与度(原則1/2)
→2,000万円 ×(20年 ÷ 40年)× 1/2 = 500万円
つまり、財産分与として500万円が妻(または夫)に支払われることになります。
②退職前の退職金がまだ確定していない場合の分与方法
退職前で金額が確定していない退職金も、将来支給される見込みがあれば財産分与の対象になります。
ただし、分与額の算出方法には大きく2つのパターンがあります。
1.離婚時に一括で支払う方法
自己都合退職の金額ベースで評価する方法
離婚時に、一括で分与額を決めて支払う方法です。この場合、「別居時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金額」を基準に計算することがあります。
- 自己都合退職金は定年退職金より少なめ
- 将来の見込み額を使うより現実的でリスクが少ない
- 裁判所でもこの方法で評価されるケースがあります
見込み退職金額から算出する方法
将来もらう予定の退職金をそのまま現在の価値として評価すると、不公平になることがあります。
なぜなら、その金額には「何年も働いた後に受け取る利息分」が含まれているためです。
そのため、離婚時に一括で支払う場合は、将来の利息分を差し引いた「現在価値」での計算が必要です。
法律用語ではこれを「中間利息控除」と呼びます。
この処理により、退職金支給時に分与する場合よりも一括支払いの金額は低くなります。
2.退職時に支払う方法
もう一つは、将来退職金が支給された時点で分与額を決める方法です。
調停や公正証書で取り決めを行い、支給された退職金から分与分を受け取ります。
熟年離婚で退職金はどうなる?重要な財産とその注意点
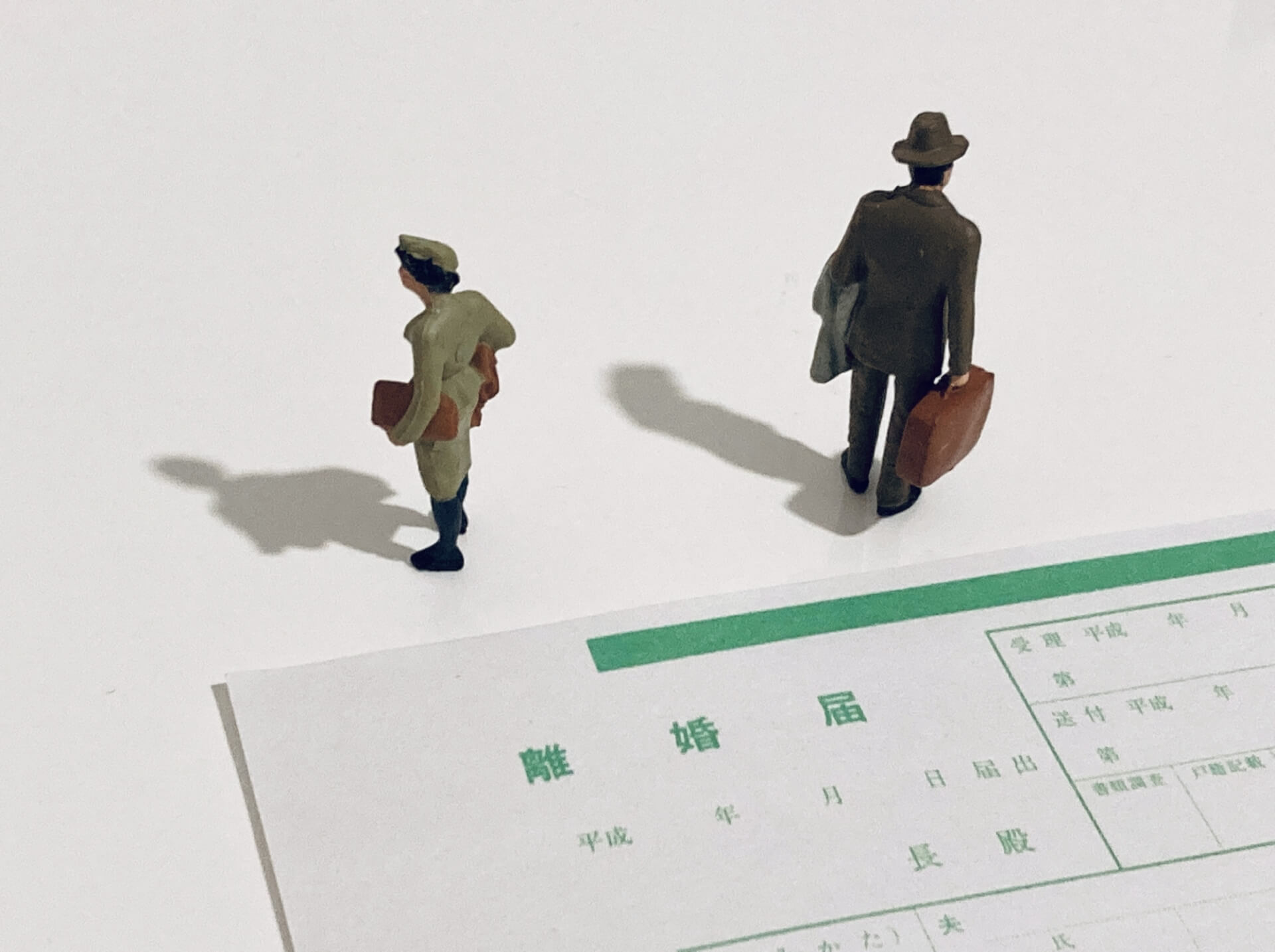
熟年離婚では、退職金が夫婦の財産の中で最も大きな資産になることも珍しくありません。
夫や妻がすでに退職している場合や、近いうちに退職予定の場合は、退職金の取り扱いが生活設計に大きく影響します。そのため、受け取り済みか、まだこれからかによって分与方法や計算方法も変わります。
退職金を一方的に使われてしまった場合
「自分が働いて得たお金だから」と、退職金を一方的に使い込むケースがあります。
- 財産分与の基準時は通常「別居開始時」
- 別居時に退職金が手元になければ、原則として財産分与の対象外
しかし、離婚を見越して財産を隠す「財産隠し」があった場合は別です。
使い込まれた金額や隠された財産も、分与対象として取り戻せる可能性があります。
DV・モラハラ・離婚で弁護士をお探…

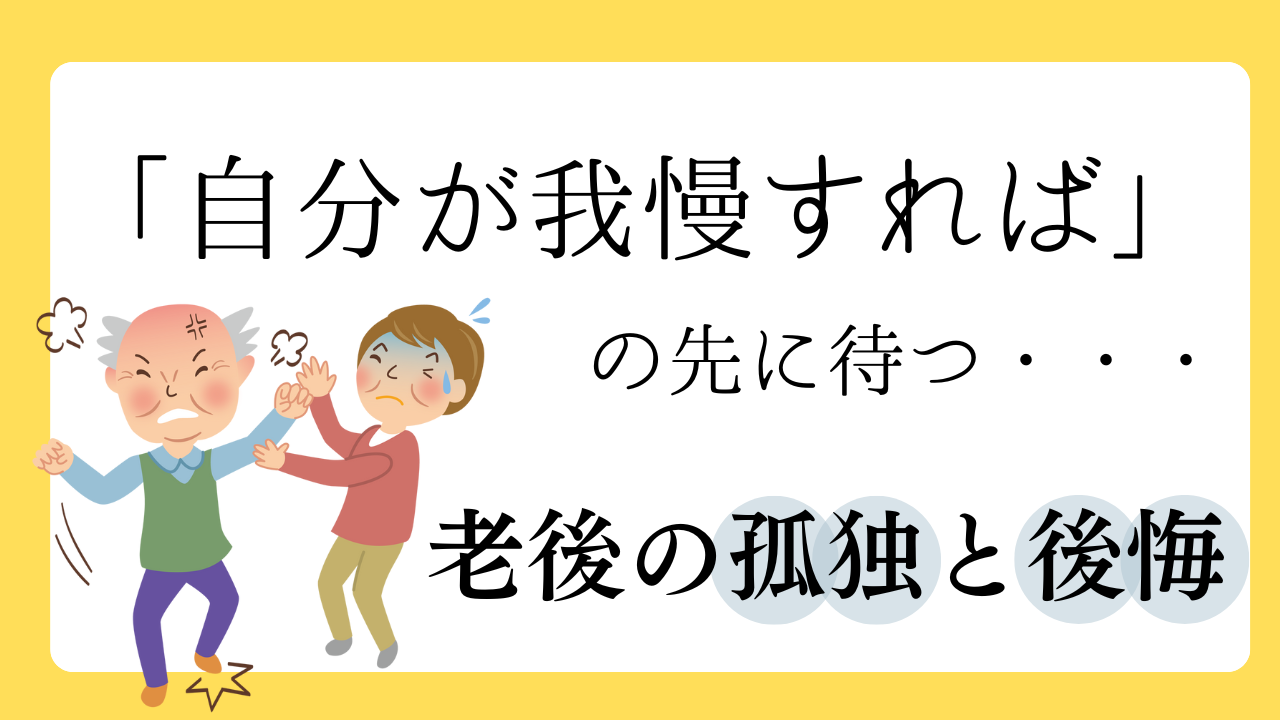
モラハラを我慢し続けた先に待つ老後の孤独と後悔-今からでも遅くない新たな選択肢 | DV・モラハラ・離婚…
長年、モラハラに耐え続けてきたあなたにとって、これまでの生活がどれほど辛いものであったか想像に難くありません。もしかしたら、「自分が我慢すれば、家族がうまくいく…
退職金の財産分与で注意すべき3つのポイント

離婚時の退職金は大きな財産になるため、金額や分与のタイミングをめぐってトラブルになりやすいです。
特に熟年離婚では生活設計にも直結するため、次の点に注意しましょう。
1.相手が退職金の情報を隠す場合
退職金の支給予定額や時期を相手が開示しないことがあります。
正確な情報がなければ、公正な財産分与はできません。
対策:弁護士を通して開示請求を行い、支給額や時期を明確にしておきましょう。
2.相手が分与を認めない場合
「退職金は自分のもの」「まだもらっていないから関係ない」と、財産分与の対象を否定するケースもあります。
しかし、婚姻期間中に形成された退職金相当部分は共有財産として評価される可能性があります。
対策:主張の整理と証拠の提示で、適切に対応することが重要です。
3.将来の退職金の評価や計算が複雑
退職前で金額が確定していない場合は、見込み額から分与額を算出する必要があります。
現在価値に割り引く「中間利息控除」や、自己都合退職時の支給額を参考にするなど、計算方法も複雑になりがちです。
対策:専門家の判断を仰ぎ、早めに弁護士へ相談することが安心です。
まとめ|退職金の取り扱いに迷ったら専門家にご相談を
退職金は財産分与の中でも判断が難しく、個別の事情によって結果が大きく変わる要素です。
- 退職金が財産分与の対象になるか
- 婚姻期間に応じた取り分はいくらか
- 見込み額をどう評価すべきか
これらを正確に判断し、公正な分与を進めるためには、法律の専門知識と実務経験が欠かせません。
退職金の取り扱いでお悩みの際は、まずは専門家に相談することをおすすめします。