OUR STRENGTHS
料金体系と当事務所の強み

- 「相談はベテランの先生だったのに、実際の対応は新人弁護士だった」
- 「費用は安かったけれど、担当の弁護士に自分の気持ちや希望がちゃんと伝わっていなかった」
- 「安く依頼したけれど、DVモラハラの手口に対する理解が浅く、相手の策略にはまってしまった」
――こうした声を、他の事務所に依頼した方から聞くことがあります。
人生を大きく左右する離婚事件、とくにDV・モラハラが絡む案件は、誰がどこまで対応するのかが結果に直結します。
当事務所の費用は、安さを売りにしている事務所と比べて安くはありません。
けれど、それには理由があります。
ここでは、当事務所の費用の考え方や、他の事務所との違いについて率直にお伝えします。
当事務所に依頼した場合にかかる離婚事件の弁護士費用について
当事務所の弁護士費用は、以下を合計した金額になります。
着手金+基本報酬金+経済的利益に基づく報酬金(+業務量、困難度、複雑性、所要時間等による加算)+実費
それぞれの項目について、詳しく説明していきたいと思います。
着手金について
離婚事件を弁護士に依頼する際、まず必要になるのが「着手金」です。
これは、事件の結果にかかわらず、依頼時に支払う費用のことをいいます。
たとえば、「離婚協議をお願いしたい」「調停・裁判をお願いしたい」といった依頼に対し、弁護士がその業務に着手するために受け取るものです。
なお、着手金を払ったからといって、必ずしも「勝てる」「離婚できる」「希望する条件を獲得する」という保証があるわけではありません。
あくまで、依頼に対して弁護士が動き始めるための対価です。
以下が、当事務所の着手金になります。
| 事件の種類 | 着手金 |
|---|---|
| 離婚事件 | 44万~66万 |
| 協議から調停、調停から審判・裁判等、別の手続に移行する場合 | 別途追加料金が発生 |
※親権について争いがある場合、上記以外に弁護士費用が加算されます。
基本報酬金について
当事務所では、報酬金を「基本報酬金」と「経済的利益に対する報酬金」に分けてご説明しています。
このうち「基本報酬金」とは、依頼者の望む結果が得られたかどうかに応じて発生する報酬です。
たとえば、離婚が成立した、親権が認められた、離婚を回避して関係を修復できた、といったように、ご依頼時の目的が達成されたかどうかを基準に判断します。
また、裁判が進行する中で、依頼者ご自身の希望が変化することもあります。
たとえば、当初は「離婚したい」と考えていた方が、話し合いや裁判の過程で「やはり再構築したい」というお気持ちに変わり、結果的に裁判を取り下げたようなケースでも、最終的に依頼者の望む結果が得られたと判断される場合には、基本報酬金が発生します。
「形式的に離婚できたかどうか」ではなく、依頼者にとっての納得のいく解決が得られたかを重視した報酬体系となっています。
| 事件の種類 | 基本報酬金 |
|---|---|
| 離婚事件 | 44万~66万 |
| 協議から調停、調停から審判・裁判等、別の手続に移行する場合 | 別途追加料金が発生 |
※親権について争いがある場合、上記以外に弁護士費用が加算されます。
経済的利益に基づく報酬金について
経済的利益とは?
離婚事件で「経済的利益」という言葉をよく耳にするかもしれません。
これは、依頼者が調停・裁判や交渉で得られる「お金や金銭的なメリット」のことを指します。
例えば、養育費や慰謝料、財産分与などで「将来もらえるお金」や「相手に支払ってもらえるお金」の総額が経済的利益です。
経済的利益のうち何%という形で、経済的利益に基づく報酬金を算出しています。
経済的利益の具体的計算方法
- 弁護士が交渉し、子どもの養育費月7万を獲得した。
→養育費については、7年分を経済的利益として計算。受給期間が7年を下回る場合は、養育費の合計額を経済的利益とします。7万×12ヶ月×7年=588万円が経済的利益になります。 - 慰謝料500万を獲得した。
→500万円が経済的利益になります。 - 財産分与として、5000万円の土地建物を獲得した。
→5000万円が経済的利益になります。 - 1,000万円相当の妻名義の自宅について、妻が自宅を取得する代わりに、夫に財産分与として500万円を支払った。
→共有財産1,000万円のうち、妻が確保した財産分である500万円が、経済的利益となります。 - 婚姻費用月12万を獲得した。
→婚姻費用調停申立から離婚成立まで、10ヶ月間支払われた場合、12万×10ヶ月=120万円が経済的利益になります。
経済的利益に基づく報酬金額
算出した経済的利益の合計に基づき、下記の表から経済的利益に基づく報酬金が決まります。
以下が、当事務所の経済的利益に基づく報酬金になります。
| 経済的利益の額 | 経済的利益に基づく報酬金額 |
|---|---|
| 300万円まで | 16%+消費税 |
| 300~3,000万円 | 10%+180,000円+消費税 |
| 3,000万円~3億円 | 6%+1,380,000円+消費税 |
| 3億円以上 | 4%+7,380,000円+消費税 |
例えば、財産分与500万円、養育費月5万円の場合、財産分与の経済的利益500万円+養育費の経済的利益420万円(5万×12ヶ月×7年)=920万円が経済的利益の額です。
上の表から、経済的利益に基づく報酬金は920万円×10%+180,000円+消費税10%=121万円になります。
業務量、困難度、複雑性、所要時間等による加算について
DVやモラハラが関係する離婚事件では、準備書面や証拠資料の作成に加え、相手方弁護士との細かいやりとり、裁判所への対応など、通常の離婚事件と比べて大幅に負担が大きくなる傾向があります。また、事件も長期化しやすく解決までに2~3年以上かかるケースも珍しくありません。
そのため当事務所では、業務の量、事件の困難さ、手続きの複雑さ、対応に要する期間などを踏まえて、弁護士報酬に加算をさせていただく場合があります。
日当、交通費等の実費について
弁護士費用とは別に、「実費」として収入印紙代・郵送料・交通費などが発生します。これは裁判所への提出書類や移動に必要な費用です。
その他、証拠や資料提出の際にかかったカラーコピー代金もいただいております。
また、裁判所の場所や出廷回数によっては、日当が発生する場合があります。
弁護士報酬における注意点

相手から提示してきた条件でも、取り決めをしたら経済的利益になります。
「この条件は相手から言い出したことで、弁護士の力で成立させたのではない」と思ってしまいがちですが、その条件が正式な取り決めとなるためには、法的に有効な形で合意に導く必要があります。
たとえ相手が提示してきた条件であっても、交渉や調停、裁判の場で確実に書面化し、将来的に支払いが継続されるように取り決めることには、弁護士の専門的な関与が不可欠です。
また、DV・モラハラなどの案件では、相手の発言が一貫せず、突然条件を変えてきたり、後から「そんなことは言っていない」と主張するケースも少なくありません。
そのため、最終的に「有効な合意」として成立させることこそが、弁護士の重要な役割であり、その成果が“経済的利益”と評価されます。
途中でご依頼を中止(解任)された場合でも、進行状況によっては弁護士報酬が発生することがあります。
たとえば、長期間にわたって離婚裁判を行った末に、弁護士を解任し最終的に訴えを取り下げる等をされた場合などです。
このような場面で「もう弁護士はいらないので解任します。費用も支払いません」と主張したとしても、事件の進行に応じて弁護士が行ってきた業務に対しては、契約に基づき報酬が発生します。
弁護士に依頼した事件の途中で解約された場合でも、一定の報酬が発生する理由は以下の通りです。
たとえば、裁判の過程で弁護士が財産分与に関する資料や証拠を収集・作成し、依頼者の利益となる主張を構築したとします。
この段階で弁護士を解約したとしても、作成された資料や証拠、及び主張の内容は依頼者の手元に残ります。
仮にその後、依頼者がこれらの資料や主張をもとに、弁護士の関与なしに当事者間だけで協議し、弁護士費用を支払わずに財産分与を行ったとすれば、弁護士の業務の成果を無償で活用することになります。
したがって、中途解約の場合でも、弁護士がそれまでに提供した業務の価値に見合った報酬をお支払いいただくことが、公平かつ合理的な取り扱いとされています。
民法においても中途解約の場合の報酬について規定が定められています(民法130条1項、民法536条2項、民法648条3項、民法648条の2、民法651条2項等)。
将来、相手から支払ってもらう予定の経済的利益(養育費など)についても、弁護士報酬は離婚時に一括でお支払いいただきます。
「まだ相手から一円ももらっていないのに、なんで先に報酬を払わなきゃいけないの?」と思われるかもしれません。
たしかに、養育費は長期間にわたって支払われるものですし、実際に支払われるかどうか不安に感じる方も多いと思います。
しかし、弁護士報酬は「支払われたかどうか」ではなく、相手に支払義務のある合意を成立させたことに対して発生し、一括で精算していただくことが一般的です。
つまり、将来的に養育費が支払われるという「法的に有効な取り決め」が成立した時点で、弁護士としての成果が出たと見なされます。
当事務所に依頼するメリット

大手事務所との違い――最後まで、所長弁護士が責任をもって対応します
当事務所では、弁護士歴18年の所長弁護士が、すべての案件を一貫して担当しています。
初回のご相談から、受任、交渉、調停、裁判、そして解決後のアフターフォローに至るまで、事務所の看板を背負った所長弁護士として最後まで責任を持って対応いたします。この点は、当事務所が他の大手事務所とは大きく異なる点です。
大手事務所では、相談時には経験豊富な弁護士が対応しても、受任後は新人や別の担当に引き継がれる、あるいは経験の浅い弁護士が事件を担当する、といった運用が多いようです。また、担当していた弁護士が転職によって担当を外れてしまう話も聞きます。
離婚事件では、相談時の話だけでは見えてこない複雑な事情が、手続きの中で次々に明らかになることがあります。
だからこそ、最初から最後まで一人の弁護士が一貫して対応することが、深い理解と的確な判断につながるのです。
また、離婚が成立すれば、すべてが解決する――というわけではありません。
むしろ、離婚成立後にこそ、新たな生活への不安や悩みが生じることもあります。
たとえば、元配偶者からの嫌がらせが続く場合、役所での手続きに関する疑問、子どもとの生活における悩みなど、「これからどうすればいいのか」と立ち止まってしまう場面は少なくありません。
当事務所では、アフターフォローとして、離婚後のご相談や困りごとに対し、必要な対応や助言をしながら、新しい一歩を安心して踏み出せるようサポートしています。
裁判所に伝わる、説得力ある主張構築が強みです
近年では、メディアやSNSで積極的に発信する弁護士も多く見られます。
広告やネット上での存在感によって、「この先生なら信頼できそう」と感じる方も少なくありません。
しかし、そうした弁護士が提出する主張書面を実際に見ると、法律的な裏付けや戦略に欠ける内容であることも少なくありません。
弁護士の役割は、単に依頼者の言い分を代弁することではなく、裁判官や調査官に伝わる形で、依頼者の立場や法的正当性を主張として構成することにあります。
当事務所では、長年の実務経験から得た視点と分析力をもとに、表面的な主張ではなく「本当に戦える主張」を大切にしています。
モラハラ加害者にありがちな、“被害者を装った主張”や感情的なアピールに流されることなく、必要な証拠と論理を積み重ね、裁判所が納得し動くだけの根拠と説得力を備えた主張を構築します。
それこそが、結果につながる弁護士の仕事であり、依頼者のこれからの人生を支える土台になると考えています。
DV・モラハラが絡む離婚事件――対応には専門性と覚悟が必要です
DVやモラハラが関係する離婚事件は、弁護士にとっても非常に負担の大きい分野です。
離離婚に伴い、お金の問題・子どもの問題・生活の問題など、さまざまな論点が絡み合い、きめ細やかな対応が求められる上に、相手方がパーソナリティに問題を抱えていることも少なくありません。
加害者が逆恨みで嫌がらせを繰り返し、平然と嘘をついて事実をねじ曲げたり、調停・裁判の場を混乱させることも珍しくありません。こうした非常に対応の難しい事件になることから、積極的に関わりたがらない弁護士も多いのが現実です。
DV・モラハラの「構造」を裁判所に理解させる難しさ
モラハラやDVの本質である「支配」や「暴力」の構造は、夫婦という密室の中で進行することが多く、裁判所に理解してもらうには相当の工夫と努力が必要です。
明確な証拠が残っていないことも多く、逆に加害者側から不利な証拠を出されることすらあります。
その中で、本質的な関係性――誰が被害者で、誰が支配しているのか――を正確に見極め、主張を組み立てられる弁護士は限られています。
当事務所では、18年にわたり多数のモラハラ・DV事件に取り組み、調停委員や裁判官に対してその構造を粘り強く説明し、被害者の立場が正しく評価されるよう尽力してきました。
特にこうした事件では、経験の深さと支配構造への理解の深さが、結果に大きく影響する分野だと実感しています。
監護者指定はじめ、DV・モラハラに関わる重要手続きについて
DV・モラハラ案件においては、監護者指定(別居中、どちらの親が子どもを育てるかを家庭裁判所に決めてもらう手続き)や子の引渡し(子どもを連れ去られた場合などに、正当な監護者のもとに戻すための手続き)、保全処分(監護者指定等審判に関する裁判所の判断が出る前に、子どもの安全を守るための仮の措置を求める手続き)などが極めて重要な局面となることが多くあります。
これらの手続きは、子どもの安全と安定を確保するために早期の対応が求められる手続きです。
一方で、スピードだけでは不十分です。監護者としての適格性を裁判所に理解してもらうためには、依頼者が子の監護にふさわしい理由を、十分かつ丁寧に主張することが欠かせません。
その内容は非常に精緻な構成が求められ、実際に50ページを超える主張書面を提出することも珍しくなく、また証拠も膨大になります。それだけの情報量と説得力が必要なのです。
監護者指定事件の特徴として、双方が「相手がDV・モラハラ加害者だ」と主張し合うケースが非常に多く見られます。
これは、モラハラ加害者がよく使う典型的な反論パターンでもあります。
こうした中で、こちらが明確な証拠をもって冷静に反論しなければ、裁判官や家庭裁判所調査官の心証に悪影響を与えてしまう可能性もあります。
このように監護者指定・子の引き渡し・保全処分の一連の事件は、特殊な手続きであり、親の人生、子どもの人生を左右する非常に重大な局面です。
にもかかわらず、この分野に十分な経験がない弁護士や、十分な熱意をもって書面を作成していない弁護士も少なくないのが現実です。
弁護士にとっては、相手の弁護士の力量や本気度は、提出された書面を見ればすぐに分かるものです。
しかし、依頼者の方にとっては、弁護士の実力を見極めるのは難しく、信じるしかないというのが現実かもしれません。
その結果、十分な対応をしてもらえなかったり、不利な条件で手続きを終えてしまうこともあり、それは本当に悔しく、納得のいかない経験だと思います。
当事務所では、こうした監護者指定事件やDV・モラハラ事案において、主張書面に決して妥協しません。
必要な論点を丁寧に積み上げ、たとえ書面が膨大な量になっても、裁判所に理解してもらえるよう工夫し続けています。
この分野では、途中で諦めず、ねばり強く的確な主張を継続することが何より大切です。
私自身、この粘り強さと構造理解に基づいた主張こそが、自分の負けない強みだと思っています。
なぜ当事務所を選ぶのか
当事務所には、以下のようなお悩みを抱えた方が多くご相談にいらっしゃいます。
- 相手が狡猾で執拗なモラハラ加害者であり、親権を激しく争っている
- 周囲は誰も理解してくれないから、DVやモラハラについて的確に対応できる弁護士を探している
- 長年苦しみ続けてきて、自分がモラハラ被害にあっているのかも分からない
- 離婚を考えているが、理不尽で強引な相手との対立に大きな不安を感じている
このように、DVやモラハラの問題に悩み、相手の巧妙なやり口に翻弄されてきた方々が、「離婚となれば穏便には済まない」と覚悟しながらも、解決を求めて相談に来られます。
実際、事件は複雑かつ困難で、監護者指定や子の引渡し、面会交流などの付随事件も加わり、長期化することも少なくありません。結果として、費用面のご負担が大きくなる場合もあります。
それでも、最終的には「この事務所に頼んでよかった」と言ってくださる方が多くいらっしゃいます。
それは、お金では代えられない「子どもとの安全な生活」や、「自分らしく生きられる新しい人生のスタート」を手に入れることができたからです。
私たちも、その思いに応えるべく、すべての案件に全力で向き合っています。
困難な状況の中で一歩を踏み出す勇気を、しっかりと支えます。
最後に──弁護士選びは、値段だけでは決めないでほしい
離婚、とくにDVやモラハラが関係するような複雑で困難な事件では、「誰に依頼するか」が、その後の人生に大きな影響を与えます。
弁護士の力量には、実際のところかなりの差があります。
費用が安くても、相手の策略に対応できず、望んだ結果が得られなければ、かえって高くつくこともあるのです。
養育費や親権、監護者の指定、面会交流といった問題は、すべてお子さんの将来や、ご自身の人生設計に関わる重要なテーマです。
だからこそ、「価格」だけではなく、「その弁護士がどれだけ専門性と経験を備え、難しい案件に対応できるか」「本当に信頼して任せられるか」という観点から、しっかりと見極めていただきたいと願っています。
当事務所では、初回のご相談からすべて所長弁護士が直接対応しております。また、必ずしもご依頼いただく必要はなく、ご相談のみでも承っております。
当事務所の法律相談は、「受任ありき」ではなく、相談者の方の問題解決そのものを目的としています。
そのため、有料相談となりますが、受任前提の無料相談とは異なり、限られた時間の中でも実質的に役立つアドバイスや方針をご提供できるよう努めております。
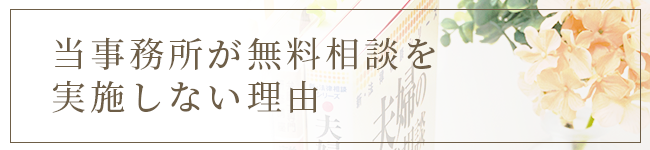
「こんなことで相談していいのかな」と思うようなことでも、どうぞ遠慮なくご相談ください。
まずは一歩、あなたの不安や疑問を言葉にしてみることが、状況を変える第一歩になります。
あなたのこれからの人生が、少しでも安心できるものになるよう、心から願っています。

